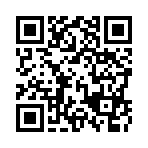2015年05月07日
高野山町石道
連休中、麓の九度山から高野山までの「高野山町石道」を歩いてきました。さて、この町石道ですが、これは弘法大師が母に会うために通った道を言うようです。弘法大師の母は息子(空海)の開いた山を一目見たいと思い、讃岐の国から訪れましたが、女人禁制の山なので、たとえそれが母親でも入山禁止。母親は九度山の政所(慈尊院)に滞在してここから、祈りを捧げていたよう。そのことに感動した空海が月に九度は山を下りたという逸話。地名の「九度山」の由来はココにあるようですね
夜中に出発して、道の駅「柿の郷くどやま」にて車中泊しました。以前行った日に、目星をつけてた駐車場は時間制限があって、夜中にはロープが張られて駐車できず
真田庵近くのP 六文銭が目印 夜間は駐車不可。 九度山駅から近いココにしようと思ったが残念

道の駅を5時に出発し、まずは慈尊院をめざします。
慈尊院も秘仏公開。女人高野のいわれのため ここは女性の乳房を模った絵馬が奉納されております。

そのすぐ先に丹生官省符神社。階段を上がるとすぐ
狩場明神と2匹のワンコ 弘法大師を高野山へと導いた神です

丹生官省符神社から脇に町石道があります。柿の畑を通り抜けます

先日購入したフォックスファイヤーのスコーロンを着こんでます。上半身はMサイズを購入。しかし家で気付いたけど、袖が長い。やっぱ試着してから買うべきだった。メーカーで長さが違うんだよな~。

道標の町石はかなりデカい。3Mくらいあるんじゃないか?1町(109M)ごとに配置してある。平安時代は木製の卒塔婆だったが老朽化のため、鎌倉時代に石に変更。約20年かけて整備されたようです。当然今のように車などあるわけもなく、馬とか牛に牽かせて、長い歳月をかけて・・・・ 苦労が偲ばれます。ちなみに8割以上が建立当時のままの町石です

柿の畑を抜けて、雨引山分岐点を通過し、7時ごろ六本杉に到着。ここから町石道をそれて世界遺産の「丹生都比売神社」へ寄り道しました

町石道をたんたんと辿りたい方はそのまま古峠へ。こちらのルートのが平坦です。丹生都比売神社へは下り坂。
丹生都比売神社の輪橋 淀君の寄進らしい(7:30)


室町時代に建立の楼門も朱色ですね。熊野速玉大社みたい ちなみに「丹」は「朱」のことで魔除けのために使われるのだとか
ちなみに祭られているのは女神で、天照大御神の妹さん「稚日女命」

本殿には近づけないので、見えるところから撮影。第一殿から第四殿ある。この創り、熊野本宮大社や速玉と同じですね

ここから二つ鳥居まで登り坂
途中にあったお遍路シール?どこで売ってるんだろう・・・

二ツ鳥居に着きました 当時は木製だったよう

近くの展望台から天野の里が一望できる

二ツ鳥居から下り坂、町石道はゴルフ場の脇を通っています。「ゴルフボールに注意」の看板や、対イノシシ用の電気柵など。
笠木峠で一休みしてから町石道は国道370号に沿っての上の方についている。バイクの音がけたたましい。
喧騒の中、我々の道中を見守る小さきお地蔵さん

矢立に到着。ここの茶屋で一福します(10時)

やきもちを二ついただきま~す

冷たいお茶もいただき、ここから先の登り坂に備えます
弘法大師にまつわる石を見やりながら大門まで一気に行きました
袈裟掛石 この石の隙間を通れると長生きするらしい。私には無理っす 子供しか通れないんじゃね?

白装束の方とすれ違い、大門に正午ごろ到着 麓の九度山から7時間かかりました

ここから壇上伽藍へ ここに慈尊院からの町石道「1」があります

連休中とあって人がかなり多い。せっかくきたのだから自分へのご褒美と精進料理でも奮発して食べようかと思ったがどこも満席 しかたないのでコンビニの惣菜パンでガマン
しかたないのでコンビニの惣菜パンでガマン
壇上伽藍を散策します
高野山の守護神を祀る御社 丹生都比売神社から勧請した神を祀る 女人禁制だった時代なのに女神はOK?

西塔は根本大塔にくらべてシックな感じ ただこっちのが落ち着いた感じでいいですね

御朱印は長蛇の列 なにがそんなにいいのかな・・・

六角経蔵 基壇付近にある取っ手がついていて、これで一周することによって一切経を一通り読経した功徳得られるという。ただし大人数人がいないと動かない お遍路さんたちが動かしては歓喜しておりました

霊宝館に再び訪問して、秘仏拝見。すごい人だかりで見るのも一苦労します。お土産に生ごま豆腐を購入して、女人堂へ向かう。せっかくだし端っこまで歩きました
女人禁制の時代に女性のための参籠所 現存する唯一の建物 ここでも御朱印の列が!
ここには弁財天が祀られておりました

ここからバス待ち 高野山駅までバス専用道路で行きます。連休中とあって臨時がでていましたよ。駅で切符を買いケーブルカーに
満車で一本見送りましたが、車両の下に極太ケーブルがありこれで車両を上げ下げしているのだろう。アプト式とは違うんですね

極楽橋駅に到着 1番線に入線する折り返しの普通列車橋本行きを待ちます
こっちは特急こうや 普段の赤と白のカラーリングとは違いますね。 ちなみに特急券はすべて売り切れだそう

橋本行きの普通列車には座れず九度山まで立ちっぱなし。疲労のせいか立ったままうたた寝してしまう。そのたびに膝がカクンとなり、ハッと目が覚めます。 久々に南海に乗れたよ

駅から道の駅まで歩いて「高野山町石道」の踏破完了です

参考書籍 楽学ブックス 古寺巡礼「高野山」 JTBパブリッシング
参考地図・時間配分等 わかやま観光情報よりダウンロード・印刷できます

夜中に出発して、道の駅「柿の郷くどやま」にて車中泊しました。以前行った日に、目星をつけてた駐車場は時間制限があって、夜中にはロープが張られて駐車できず
真田庵近くのP 六文銭が目印 夜間は駐車不可。 九度山駅から近いココにしようと思ったが残念
道の駅を5時に出発し、まずは慈尊院をめざします。
慈尊院も秘仏公開。女人高野のいわれのため ここは女性の乳房を模った絵馬が奉納されております。
そのすぐ先に丹生官省符神社。階段を上がるとすぐ
狩場明神と2匹のワンコ 弘法大師を高野山へと導いた神です
丹生官省符神社から脇に町石道があります。柿の畑を通り抜けます
先日購入したフォックスファイヤーのスコーロンを着こんでます。上半身はMサイズを購入。しかし家で気付いたけど、袖が長い。やっぱ試着してから買うべきだった。メーカーで長さが違うんだよな~。
道標の町石はかなりデカい。3Mくらいあるんじゃないか?1町(109M)ごとに配置してある。平安時代は木製の卒塔婆だったが老朽化のため、鎌倉時代に石に変更。約20年かけて整備されたようです。当然今のように車などあるわけもなく、馬とか牛に牽かせて、長い歳月をかけて・・・・ 苦労が偲ばれます。ちなみに8割以上が建立当時のままの町石です
柿の畑を抜けて、雨引山分岐点を通過し、7時ごろ六本杉に到着。ここから町石道をそれて世界遺産の「丹生都比売神社」へ寄り道しました
町石道をたんたんと辿りたい方はそのまま古峠へ。こちらのルートのが平坦です。丹生都比売神社へは下り坂。
丹生都比売神社の輪橋 淀君の寄進らしい(7:30)
室町時代に建立の楼門も朱色ですね。熊野速玉大社みたい ちなみに「丹」は「朱」のことで魔除けのために使われるのだとか
ちなみに祭られているのは女神で、天照大御神の妹さん「稚日女命」
本殿には近づけないので、見えるところから撮影。第一殿から第四殿ある。この創り、熊野本宮大社や速玉と同じですね
ここから二つ鳥居まで登り坂
途中にあったお遍路シール?どこで売ってるんだろう・・・
二ツ鳥居に着きました 当時は木製だったよう
近くの展望台から天野の里が一望できる
二ツ鳥居から下り坂、町石道はゴルフ場の脇を通っています。「ゴルフボールに注意」の看板や、対イノシシ用の電気柵など。
笠木峠で一休みしてから町石道は国道370号に沿っての上の方についている。バイクの音がけたたましい。
喧騒の中、我々の道中を見守る小さきお地蔵さん
矢立に到着。ここの茶屋で一福します(10時)
やきもちを二ついただきま~す
冷たいお茶もいただき、ここから先の登り坂に備えます
弘法大師にまつわる石を見やりながら大門まで一気に行きました
袈裟掛石 この石の隙間を通れると長生きするらしい。私には無理っす 子供しか通れないんじゃね?
白装束の方とすれ違い、大門に正午ごろ到着 麓の九度山から7時間かかりました
ここから壇上伽藍へ ここに慈尊院からの町石道「1」があります
連休中とあって人がかなり多い。せっかくきたのだから自分へのご褒美と精進料理でも奮発して食べようかと思ったがどこも満席
 しかたないのでコンビニの惣菜パンでガマン
しかたないのでコンビニの惣菜パンでガマン壇上伽藍を散策します
高野山の守護神を祀る御社 丹生都比売神社から勧請した神を祀る 女人禁制だった時代なのに女神はOK?
西塔は根本大塔にくらべてシックな感じ ただこっちのが落ち着いた感じでいいですね
御朱印は長蛇の列 なにがそんなにいいのかな・・・
六角経蔵 基壇付近にある取っ手がついていて、これで一周することによって一切経を一通り読経した功徳得られるという。ただし大人数人がいないと動かない お遍路さんたちが動かしては歓喜しておりました

霊宝館に再び訪問して、秘仏拝見。すごい人だかりで見るのも一苦労します。お土産に生ごま豆腐を購入して、女人堂へ向かう。せっかくだし端っこまで歩きました
女人禁制の時代に女性のための参籠所 現存する唯一の建物 ここでも御朱印の列が!
ここには弁財天が祀られておりました
ここからバス待ち 高野山駅までバス専用道路で行きます。連休中とあって臨時がでていましたよ。駅で切符を買いケーブルカーに
満車で一本見送りましたが、車両の下に極太ケーブルがありこれで車両を上げ下げしているのだろう。アプト式とは違うんですね
極楽橋駅に到着 1番線に入線する折り返しの普通列車橋本行きを待ちます
こっちは特急こうや 普段の赤と白のカラーリングとは違いますね。 ちなみに特急券はすべて売り切れだそう
橋本行きの普通列車には座れず九度山まで立ちっぱなし。疲労のせいか立ったままうたた寝してしまう。そのたびに膝がカクンとなり、ハッと目が覚めます。 久々に南海に乗れたよ
駅から道の駅まで歩いて「高野山町石道」の踏破完了です
参考書籍 楽学ブックス 古寺巡礼「高野山」 JTBパブリッシング
参考地図・時間配分等 わかやま観光情報よりダウンロード・印刷できます
Posted by myouzin1432 at 08:20│Comments(0)
│登山