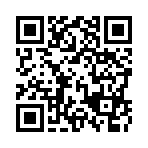2011年05月14日
ホーボーさんのチェストバッグ 他
登山のとき常用しているのが、ホーボージュンさんプロデュースのチェストバッグ。実践主義道具学に掲載されていて、便利そうなので買いました。
特徴としては、色々なモノを前方に集約して登山中バックパックを下ろさずにすむ回数が減ることでしょうか。水分は別にキャメルバックで対応。

ドラクエで言うと、「鉄の胸当て」っぽいですがここに私は、コンデジ、ライター、レザーマン、行動食、ハンディGPS(ガーミン)、地形図、コンパス、筆記用具などをいれています


やはり、必要なものをすぐに取り出せるというのが最大のメリットだと思います。これあるなしでは、全く違うとも思っています。弱点は、夏は胸の部分の風通しが悪くなること(当たり前ですが)、そして、防水性はないことでしょうか。雨対策のために私はこれで対応しました

どこにでもあるシャワーキャップです。これが今のところジャストフィット! ただ、雨の日縦走したことがありますが、シャワーキャップをつけていてもだんだん水が染み込んできます。ですから、バッグの中でもジップロックにいれたりして雨対策をしています。
ただ、雨の日縦走したことがありますが、シャワーキャップをつけていてもだんだん水が染み込んできます。ですから、バッグの中でもジップロックにいれたりして雨対策をしています。
話は変わり通信機器はドコモの携帯電話とトランシーバーを持っています。携帯電話ですがこれは大峯、台高山脈ではつながる箇所はほとんどないです。逆に北アルプスではつながりやすかった。ですから、トランシーバーは必携。もちろんアマチュア無線の免許は取得しています。持っているトランシーバーはスタンダードというメーカーのもの。

一応防水仕様だったと思います。お値段はたぶん予備のバッテリー合わせて5万円くらいだったかな~。高いですが、何かあったときのことを考えれば安いと思います。ただ、いままでまともに使ったことはありません。非常用と割り切っているので、いつもOFF。ま、良い方向に解釈すると遭難じみたことは今までないということです。 購入したお店の主人の話では、白馬岳の遭難現場でヘリコプターと降下した隊員の逼迫したやり取りを聞いたそうな・・・。
さて、この無線機とガーミンGPSを組み合わせると非常に効果的だと思います。もし最悪遭難したとき、自分の居場所を正確に伝えることが可能だと思います。使用しているガーミンGPS「レジェンド」には現在地の座標が表示されます。緯度、経度を無線で救助隊に伝えることができれば、救助する側もあちこち探さずピンポイントで捜索可能になります。 ただ前回にも書きましたが、GPSで自分の現在地が表示されたらの話で、衛星状態が悪かったり、バッテリー切れ、故障など想定されることがあります。その場合はむやみに山を下らず、尾根を目指して分かりやすいところで救助を待つのが正解だと思います。
ちなみに、私がGPS購入に際し、参考にした本はこちら、「野宿大全」です。この本を一読することをおすすめします
かなりマニアックな一冊です
あと、山漫画はこちら「でこでこてっぺん」をおすすめ!抱腹絶倒!?です

特徴としては、色々なモノを前方に集約して登山中バックパックを下ろさずにすむ回数が減ることでしょうか。水分は別にキャメルバックで対応。
ドラクエで言うと、「鉄の胸当て」っぽいですがここに私は、コンデジ、ライター、レザーマン、行動食、ハンディGPS(ガーミン)、地形図、コンパス、筆記用具などをいれています
やはり、必要なものをすぐに取り出せるというのが最大のメリットだと思います。これあるなしでは、全く違うとも思っています。弱点は、夏は胸の部分の風通しが悪くなること(当たり前ですが)、そして、防水性はないことでしょうか。雨対策のために私はこれで対応しました
どこにでもあるシャワーキャップです。これが今のところジャストフィット!
 ただ、雨の日縦走したことがありますが、シャワーキャップをつけていてもだんだん水が染み込んできます。ですから、バッグの中でもジップロックにいれたりして雨対策をしています。
ただ、雨の日縦走したことがありますが、シャワーキャップをつけていてもだんだん水が染み込んできます。ですから、バッグの中でもジップロックにいれたりして雨対策をしています。話は変わり通信機器はドコモの携帯電話とトランシーバーを持っています。携帯電話ですがこれは大峯、台高山脈ではつながる箇所はほとんどないです。逆に北アルプスではつながりやすかった。ですから、トランシーバーは必携。もちろんアマチュア無線の免許は取得しています。持っているトランシーバーはスタンダードというメーカーのもの。
一応防水仕様だったと思います。お値段はたぶん予備のバッテリー合わせて5万円くらいだったかな~。高いですが、何かあったときのことを考えれば安いと思います。ただ、いままでまともに使ったことはありません。非常用と割り切っているので、いつもOFF。ま、良い方向に解釈すると遭難じみたことは今までないということです。 購入したお店の主人の話では、白馬岳の遭難現場でヘリコプターと降下した隊員の逼迫したやり取りを聞いたそうな・・・。
さて、この無線機とガーミンGPSを組み合わせると非常に効果的だと思います。もし最悪遭難したとき、自分の居場所を正確に伝えることが可能だと思います。使用しているガーミンGPS「レジェンド」には現在地の座標が表示されます。緯度、経度を無線で救助隊に伝えることができれば、救助する側もあちこち探さずピンポイントで捜索可能になります。 ただ前回にも書きましたが、GPSで自分の現在地が表示されたらの話で、衛星状態が悪かったり、バッテリー切れ、故障など想定されることがあります。その場合はむやみに山を下らず、尾根を目指して分かりやすいところで救助を待つのが正解だと思います。
ちなみに、私がGPS購入に際し、参考にした本はこちら、「野宿大全」です。この本を一読することをおすすめします

かなりマニアックな一冊です
あと、山漫画はこちら「でこでこてっぺん」をおすすめ!抱腹絶倒!?です
2011年05月13日
ハイライトテント と ステラリッジテント2型
熊野本宮近辺のオートキャンプ場、明神平、小笹の宿といままで3回ハイライトを使いました。
やはり軽量という点では、すでに持っているモンベルのステラリッジテント2型より良いと思います。ただシングルウォールテントですので、不安は付きまといます。
ステラリッジテント2型はアウトレットで購入しました。1型と迷いましたが、広い方がいいやという安直な考えで買いましたが、後悔はしていません。ちなみに、テントでは収容人数という表示があります。これは人が何人寝られるかという考えで、荷物の事は考えていないと思います。だから購入する際、一人なら1型でも良いですけど、2人なら3型を買った方が無難です。グラウンドシートとあわせて約2300グラムあります。ハイライトと比べると重いですが、ダブルウォールということや国内メーカーという安心感はあります。雨の日なんかだとやっぱりダブルウォールは有利です。ただ、雨のとき、生地が水分を吸い込み重くなります。それと本体とフライを同じスタッフバッグに入れるのもどうかと思います。それだと濡れたフライと一緒にするわけで、本体が濡れてしまう。だから私はフライは別に衣類圧縮袋にいれてパックにつめています。こうするとコンパクトになります。あと、テントに限ったことではないですが、モンベルのスタッフバッグはきつきつです。雨とかいち早く撤収したいときに、きっちり折りたたんで収納なんて悠長なこと実際できません。これはモンベルに限ったことではなく、ハイライトもそう。こっちは気密性がよすぎて、テントを山折にすると空気が抜けず畳めない。だから私はテントのボトムを谷折にして畳んでから、というよりスタッフバッグにぐいぐい詰め込んでいます


画像は、唐松岳幕営地と大峯の某所です。ステラリッジは最初から縫い目にシーリングテープが施されており、縫い目からの浸水も防いでくれます。本体の四隅もしっかりシーリングされています。また、フライはゴムコードで本体と連結しています。これが結構重要で、ゴムの伸縮でフライの生地の伸縮を調節してくれています。
ハイライトですが、これは積雪期も使えるテントとして購入。冬山だけだと短辺側に出入り口のあるファーストライトのほうがいいでしょうが、夏にも使いたい、ある程度開放的なのがいいという考えでこちらにしました。このテントは購入してまず縫い目にシルネットで塗り塗りしなくてはいけません。それも根気よく。説明書にも書いてありますが薄く細くです。あまり厚すぎると剥離してしまう可能性があります。というより実際剥離してしまいした
冬の熊野本宮のオートキャンプ場で実践デビュー。それでその日雨が降りました。気分はブルーになりましたが、このテントの性能を見るにはうってつけです。小雨程度でしたが、雨漏り、縫い目からの浸水はありません。また、結露ですがうっすらありました。翌朝、テント表皮は水玉になって凍っていました。強力な撥水性能はあるようです。唯一の失敗はポールを素手で撤収したこと。冷た痛くてたまりませんでした。

画像は、再び明神平での様子ですが、開口部が大きいと風雨が入りやすいことは確かですが、この「庇(ひさし)」のおかげで、雨の日べスティブール(前室)なしでもある程度いけるんじゃないかとも思っています。登山靴もろもろは大きめのビニル袋に入れてテント内へ持ち込み、我慢。軽量性を重視するならこの方法になるでしょうか。

ただ、一度前室の快適性を味わってしまうともとに戻れないかも・・・これだけ広いと一人では超快適
ハイライトはインナーポール方式でテントの中に入ってポールを張ります。この方法で一番気を使うのが四隅のグロメットにポール末端をはめ込む瞬間。前にも記述しましたけど、生地が薄いのではずれで破けちゃうんじゃないかといつも心配しています。ここらへんもっと改良できたんじゃないかと思います。生地を厚くしたり多少乱暴に扱ってもグロメットに自然にポールがはまるようにするとか。ま、今こんなこと言ってもしょうがないのでなにか良い方法はないか考え中
やはり軽量という点では、すでに持っているモンベルのステラリッジテント2型より良いと思います。ただシングルウォールテントですので、不安は付きまといます。
ステラリッジテント2型はアウトレットで購入しました。1型と迷いましたが、広い方がいいやという安直な考えで買いましたが、後悔はしていません。ちなみに、テントでは収容人数という表示があります。これは人が何人寝られるかという考えで、荷物の事は考えていないと思います。だから購入する際、一人なら1型でも良いですけど、2人なら3型を買った方が無難です。グラウンドシートとあわせて約2300グラムあります。ハイライトと比べると重いですが、ダブルウォールということや国内メーカーという安心感はあります。雨の日なんかだとやっぱりダブルウォールは有利です。ただ、雨のとき、生地が水分を吸い込み重くなります。それと本体とフライを同じスタッフバッグに入れるのもどうかと思います。それだと濡れたフライと一緒にするわけで、本体が濡れてしまう。だから私はフライは別に衣類圧縮袋にいれてパックにつめています。こうするとコンパクトになります。あと、テントに限ったことではないですが、モンベルのスタッフバッグはきつきつです。雨とかいち早く撤収したいときに、きっちり折りたたんで収納なんて悠長なこと実際できません。これはモンベルに限ったことではなく、ハイライトもそう。こっちは気密性がよすぎて、テントを山折にすると空気が抜けず畳めない。だから私はテントのボトムを谷折にして畳んでから、というよりスタッフバッグにぐいぐい詰め込んでいます

画像は、唐松岳幕営地と大峯の某所です。ステラリッジは最初から縫い目にシーリングテープが施されており、縫い目からの浸水も防いでくれます。本体の四隅もしっかりシーリングされています。また、フライはゴムコードで本体と連結しています。これが結構重要で、ゴムの伸縮でフライの生地の伸縮を調節してくれています。
ハイライトですが、これは積雪期も使えるテントとして購入。冬山だけだと短辺側に出入り口のあるファーストライトのほうがいいでしょうが、夏にも使いたい、ある程度開放的なのがいいという考えでこちらにしました。このテントは購入してまず縫い目にシルネットで塗り塗りしなくてはいけません。それも根気よく。説明書にも書いてありますが薄く細くです。あまり厚すぎると剥離してしまう可能性があります。というより実際剥離してしまいした

冬の熊野本宮のオートキャンプ場で実践デビュー。それでその日雨が降りました。気分はブルーになりましたが、このテントの性能を見るにはうってつけです。小雨程度でしたが、雨漏り、縫い目からの浸水はありません。また、結露ですがうっすらありました。翌朝、テント表皮は水玉になって凍っていました。強力な撥水性能はあるようです。唯一の失敗はポールを素手で撤収したこと。冷た痛くてたまりませんでした。
画像は、再び明神平での様子ですが、開口部が大きいと風雨が入りやすいことは確かですが、この「庇(ひさし)」のおかげで、雨の日べスティブール(前室)なしでもある程度いけるんじゃないかとも思っています。登山靴もろもろは大きめのビニル袋に入れてテント内へ持ち込み、我慢。軽量性を重視するならこの方法になるでしょうか。
ただ、一度前室の快適性を味わってしまうともとに戻れないかも・・・これだけ広いと一人では超快適

ハイライトはインナーポール方式でテントの中に入ってポールを張ります。この方法で一番気を使うのが四隅のグロメットにポール末端をはめ込む瞬間。前にも記述しましたけど、生地が薄いのではずれで破けちゃうんじゃないかといつも心配しています。ここらへんもっと改良できたんじゃないかと思います。生地を厚くしたり多少乱暴に扱ってもグロメットに自然にポールがはまるようにするとか。ま、今こんなこと言ってもしょうがないのでなにか良い方法はないか考え中
2011年05月12日
ギア紹介2
登山において一番怖いのは遭難。それを回避するために私は地形図、コンパス、そしてGPSを携帯しています。
地形図はまず、読図のスキルがいります。これが分かるといま自分がどこにいるか、だいぶ検討がつきます。ちなみにコンパスとは一蓮托生!地形図は大まかな行程の把握用地図として「山と高原」の地図。そして国土地理院の2万5千分の1の地形図を使っています。コンパスはシルバコンパスを使用しています。たぶんこれがスタンダードだと思います。ただこれは使えてなんぼですので、参考書としては平塚晶人著「地図の読み方」を参考にしてください。訓練用の地形図も掲載してあります。おすすめです。あとは実際山で体験してみることです。分かってくると山歩きが面白くなりますよ
といっても、登山でガスっていたら地形もくそもないじゃん!という至極まっとうな意見はあります。実際そうで、稜線上なら進んでいる方角はわかるけど、例えば明神平や明神岳から桧塚までの広い尾根など自分のいまどどこにいるか分かりにくいところが厄介。そこで保険としてGPSを購入。ガーミンのイートレックスレジェンドHcxです。ナチュラムさんでは5万円くらいで売られていますね。私はそんなに金を掛けたくないので、アジアパシフィックバージョンを購入し、ソフトも別で買いました。これだと確か2万円くらい安くなります。お金に余裕のある人は日本語バージョンで良いと思います。私は英語でもほとんど問題ないのでこれで十分。さてどれくらい正確か?というとかなり正確です。誤差は3メートル以内!ただ、これは衛星状態が良いときで、悪いと???となり現在地が特定できない「時」もあります ま、それは愛嬌ということで私はあまり気にしていません。私の使用しているGPSですが国土地理院の地形図を入れてありますので自分のいる高度も分かりますし、歩くと自分の向かっている方角が分かります。私は現在地さえ分かれば良いので、カシミールとかは使っていません。単独だとGPSは必携だと思います。実際大峯奥駈道縦走(南部 太古の辻~熊野本宮大社)では非常に役に立ちました。「いま、ここだから、次の『行仙の宿』まであと少し。ピークを2,3越えて到着するな」という使い方ができます。
ま、それは愛嬌ということで私はあまり気にしていません。私の使用しているGPSですが国土地理院の地形図を入れてありますので自分のいる高度も分かりますし、歩くと自分の向かっている方角が分かります。私は現在地さえ分かれば良いので、カシミールとかは使っていません。単独だとGPSは必携だと思います。実際大峯奥駈道縦走(南部 太古の辻~熊野本宮大社)では非常に役に立ちました。「いま、ここだから、次の『行仙の宿』まであと少し。ピークを2,3越えて到着するな」という使い方ができます。
ツールナイフはレザーマンXe6を使用しています。これも、ホーボージュンさんの影響で購入。ただちと重い。ま、もっと重量級のモデルもあるのでそれに比べれば軽量。登山で一番使う機会が多いのが「ナイフ」と言いたいところですが、実際頻繁に使用しているのは「ハサミ」。レトルトパックのカットのときなど、食事のときに多用。あとペンチ機能は必要。モノを挟む機能はあると便利です。
以上今回はここまでです
地形図はまず、読図のスキルがいります。これが分かるといま自分がどこにいるか、だいぶ検討がつきます。ちなみにコンパスとは一蓮托生!地形図は大まかな行程の把握用地図として「山と高原」の地図。そして国土地理院の2万5千分の1の地形図を使っています。コンパスはシルバコンパスを使用しています。たぶんこれがスタンダードだと思います。ただこれは使えてなんぼですので、参考書としては平塚晶人著「地図の読み方」を参考にしてください。訓練用の地形図も掲載してあります。おすすめです。あとは実際山で体験してみることです。分かってくると山歩きが面白くなりますよ
といっても、登山でガスっていたら地形もくそもないじゃん!という至極まっとうな意見はあります。実際そうで、稜線上なら進んでいる方角はわかるけど、例えば明神平や明神岳から桧塚までの広い尾根など自分のいまどどこにいるか分かりにくいところが厄介。そこで保険としてGPSを購入。ガーミンのイートレックスレジェンドHcxです。ナチュラムさんでは5万円くらいで売られていますね。私はそんなに金を掛けたくないので、アジアパシフィックバージョンを購入し、ソフトも別で買いました。これだと確か2万円くらい安くなります。お金に余裕のある人は日本語バージョンで良いと思います。私は英語でもほとんど問題ないのでこれで十分。さてどれくらい正確か?というとかなり正確です。誤差は3メートル以内!ただ、これは衛星状態が良いときで、悪いと???となり現在地が特定できない「時」もあります
 ま、それは愛嬌ということで私はあまり気にしていません。私の使用しているGPSですが国土地理院の地形図を入れてありますので自分のいる高度も分かりますし、歩くと自分の向かっている方角が分かります。私は現在地さえ分かれば良いので、カシミールとかは使っていません。単独だとGPSは必携だと思います。実際大峯奥駈道縦走(南部 太古の辻~熊野本宮大社)では非常に役に立ちました。「いま、ここだから、次の『行仙の宿』まであと少し。ピークを2,3越えて到着するな」という使い方ができます。
ま、それは愛嬌ということで私はあまり気にしていません。私の使用しているGPSですが国土地理院の地形図を入れてありますので自分のいる高度も分かりますし、歩くと自分の向かっている方角が分かります。私は現在地さえ分かれば良いので、カシミールとかは使っていません。単独だとGPSは必携だと思います。実際大峯奥駈道縦走(南部 太古の辻~熊野本宮大社)では非常に役に立ちました。「いま、ここだから、次の『行仙の宿』まであと少し。ピークを2,3越えて到着するな」という使い方ができます。ツールナイフはレザーマンXe6を使用しています。これも、ホーボージュンさんの影響で購入。ただちと重い。ま、もっと重量級のモデルもあるのでそれに比べれば軽量。登山で一番使う機会が多いのが「ナイフ」と言いたいところですが、実際頻繁に使用しているのは「ハサミ」。レトルトパックのカットのときなど、食事のときに多用。あとペンチ機能は必要。モノを挟む機能はあると便利です。
以上今回はここまでです
2011年05月12日
動植物いろいろ
今回、熊野古道と大峯に行ったときのを紹介します

熊野古道は温暖なのでシダ植物はたくさん自生しています。あちらこちらで「グルグル巻き」が見れました

お次はカムフラージュ率ほぼ100%の蜘蛛。ふと注意してみるとこういう発見があります
荷坂峠に行く途中の民家では綺麗で規則正しい花が見れました

どうしたらこういう風になるんだろう?自然は不思議です。花の名称はわかりません
荷坂峠下山後に見たのは白い紫陽花のような花をつけた木


白いモコモコとした不思議な植物でした。ちなみにこれも名前はわかりません

大峯ではこれだけでした・・・。黄色いしわしわの麺のような花?大峯で植物が活性化するのはもうすこし後のようです。ああ、オオヤマレンゲが見てみたい
一旦立ち止まって見てみるといろいろな発見あります

熊野古道は温暖なのでシダ植物はたくさん自生しています。あちらこちらで「グルグル巻き」が見れました

お次はカムフラージュ率ほぼ100%の蜘蛛。ふと注意してみるとこういう発見があります
荷坂峠に行く途中の民家では綺麗で規則正しい花が見れました
どうしたらこういう風になるんだろう?自然は不思議です。花の名称はわかりません
荷坂峠下山後に見たのは白い紫陽花のような花をつけた木
白いモコモコとした不思議な植物でした。ちなみにこれも名前はわかりません
大峯ではこれだけでした・・・。黄色いしわしわの麺のような花?大峯で植物が活性化するのはもうすこし後のようです。ああ、オオヤマレンゲが見てみたい

一旦立ち止まって見てみるといろいろな発見あります
2011年05月08日
2日目 小笹の宿~稲村ヶ岳
3時ごろ起床。山家の朝は早い。朝食にパンを食べて、ブルックスのコーヒーを淹れ、至福のひと時。テントを撤収し、4時半くらいに出発。まずは山上ヶ岳をめざす。途中登山道から見た朝日は美しかった。バックパックからモンベルのライトカメラショルダーバッグLを取り出し、マミヤで撮影する。小型デジタル一眼ならMサイズでいいでしょうけど、中判カメラでフィルムやその他撮影用品をいれると、どうしても容量の大きいLが必要と思います。雪や砂埃から守るための工夫や、細いけどウェストベルトもあります。これで歩く際バッグの揺れを防ぎます。クッション性は必要最低限で、バックパックの中で形を変えられるから便利。ただし、防水性はありません。

山上ガ岳に到着し、これから行く稲村、大日岳が見渡せる。直線だと近いんだけどな~。

途中、日本岩により、レンゲ辻に至る。ここから稲村小屋に行く途中で落石にあいました。地形図で言う沢を横断中、上のほうで「カラカラ」と音がした。瞬間的に体が反応し走りました。直後ソフトボールほどの石がガラガラと落ちてきました。危ない危ない・・・。
稲村小屋に7時に到着。ここでしばし休憩し、稲村ヶ岳を目指す。気にしていたのが雪渓。山上ヶ岳からも残雪が見えるので心配でした。行って見ると、やはり雪渓を数箇所横断しなければなりませんでした。急斜面のトラバース道。一歩間違うと滑落です。

早朝行ったから、雪が引き締まっていて、タコ壺もあり歩きやすかった。アイゼンの装着は必要ないと思いますが、油断は禁物。危ないのは雪解けでところどころ空洞があること。ちょっと踏み抜いて怪我でもしたら大変。中途半端な雪渓はこわい。7:50稲村ヶ岳に登頂!一人なので雄叫びをひとついっときました。ここから弥山や山上ヶ岳が見渡せます。

記念撮影をして、次に大日岳へ。この山、日本昔話にあるような山容です

大日岳への分岐で小屋の主人と遭遇。主人はチェーンソーにツルハシを担いでおられ、登山道の整備にでかけるようでした。ありがたいことです。主人と別れ、大日岳に登る。ここは鎖伝いに登りました

そして、鉄の橋をわたり梯子をのぼり、ついに頂上へ!といっても10分で登頂。頂上には小さな祠がありあす
手を合わせて祈りを奉げ下山開始。登りより下りのが怖い。しかも、大きく重いバックパック。念のためカラビナとスリングを使い鎖に掛けて慎重に下りました。9時に小屋に到着。ココアをいれてホット一息していると、他の登山者が法力峠のほうからあがってきました。しばらくすると、小屋の主人も帰ってこられて、記念バッチを購入しようとしたけど、GW中に売り切れたらしい 収集している自分として残念でした。9時半下山開始。法力峠を10:20通過。途中ちらほら、山ガ~ルとすれ違いました。一人で山へ行く若い女性も多いんですね~。ただ、あまりにも装備が軽装過ぎるのと、登る時間が10時ごろと遅いのが心配。無事だと良いんですが。寺にも行方不明者の張り紙がありました。気をつけなればいけません。11時に母公堂につきました。母公堂も開いており、中を見ることができラッキー。役行者の母の像が安置されていました。帰りに杉の湯川上のホテルの温泉につかり、体を洗い、疲れをいやしました。途中、柿の葉すしを購入し家路につきました。
収集している自分として残念でした。9時半下山開始。法力峠を10:20通過。途中ちらほら、山ガ~ルとすれ違いました。一人で山へ行く若い女性も多いんですね~。ただ、あまりにも装備が軽装過ぎるのと、登る時間が10時ごろと遅いのが心配。無事だと良いんですが。寺にも行方不明者の張り紙がありました。気をつけなればいけません。11時に母公堂につきました。母公堂も開いており、中を見ることができラッキー。役行者の母の像が安置されていました。帰りに杉の湯川上のホテルの温泉につかり、体を洗い、疲れをいやしました。途中、柿の葉すしを購入し家路につきました。
山上ガ岳に到着し、これから行く稲村、大日岳が見渡せる。直線だと近いんだけどな~。
途中、日本岩により、レンゲ辻に至る。ここから稲村小屋に行く途中で落石にあいました。地形図で言う沢を横断中、上のほうで「カラカラ」と音がした。瞬間的に体が反応し走りました。直後ソフトボールほどの石がガラガラと落ちてきました。危ない危ない・・・。
稲村小屋に7時に到着。ここでしばし休憩し、稲村ヶ岳を目指す。気にしていたのが雪渓。山上ヶ岳からも残雪が見えるので心配でした。行って見ると、やはり雪渓を数箇所横断しなければなりませんでした。急斜面のトラバース道。一歩間違うと滑落です。
早朝行ったから、雪が引き締まっていて、タコ壺もあり歩きやすかった。アイゼンの装着は必要ないと思いますが、油断は禁物。危ないのは雪解けでところどころ空洞があること。ちょっと踏み抜いて怪我でもしたら大変。中途半端な雪渓はこわい。7:50稲村ヶ岳に登頂!一人なので雄叫びをひとついっときました。ここから弥山や山上ヶ岳が見渡せます。
記念撮影をして、次に大日岳へ。この山、日本昔話にあるような山容です
大日岳への分岐で小屋の主人と遭遇。主人はチェーンソーにツルハシを担いでおられ、登山道の整備にでかけるようでした。ありがたいことです。主人と別れ、大日岳に登る。ここは鎖伝いに登りました
そして、鉄の橋をわたり梯子をのぼり、ついに頂上へ!といっても10分で登頂。頂上には小さな祠がありあす
手を合わせて祈りを奉げ下山開始。登りより下りのが怖い。しかも、大きく重いバックパック。念のためカラビナとスリングを使い鎖に掛けて慎重に下りました。9時に小屋に到着。ココアをいれてホット一息していると、他の登山者が法力峠のほうからあがってきました。しばらくすると、小屋の主人も帰ってこられて、記念バッチを購入しようとしたけど、GW中に売り切れたらしい
 収集している自分として残念でした。9時半下山開始。法力峠を10:20通過。途中ちらほら、山ガ~ルとすれ違いました。一人で山へ行く若い女性も多いんですね~。ただ、あまりにも装備が軽装過ぎるのと、登る時間が10時ごろと遅いのが心配。無事だと良いんですが。寺にも行方不明者の張り紙がありました。気をつけなればいけません。11時に母公堂につきました。母公堂も開いており、中を見ることができラッキー。役行者の母の像が安置されていました。帰りに杉の湯川上のホテルの温泉につかり、体を洗い、疲れをいやしました。途中、柿の葉すしを購入し家路につきました。
収集している自分として残念でした。9時半下山開始。法力峠を10:20通過。途中ちらほら、山ガ~ルとすれ違いました。一人で山へ行く若い女性も多いんですね~。ただ、あまりにも装備が軽装過ぎるのと、登る時間が10時ごろと遅いのが心配。無事だと良いんですが。寺にも行方不明者の張り紙がありました。気をつけなればいけません。11時に母公堂につきました。母公堂も開いており、中を見ることができラッキー。役行者の母の像が安置されていました。帰りに杉の湯川上のホテルの温泉につかり、体を洗い、疲れをいやしました。途中、柿の葉すしを購入し家路につきました。2011年05月08日
山上ヶ岳~稲村ヶ岳 周遊と ハイライト前室使用
GW、熊野古道とは別に、大峯山にテント泊してきました。夜中に家を出発。道の駅杉の湯川上から、林道高原洞川線を経由して五番関を通過しました。この林道夜は真っ暗で本当に怖い。路面も陥没しているところもあり、段差も結構あるので注意が必要です。5:30ごろ母公堂に到着。登山届けポストに計画書を投函し出発。まずは林道を北上し五番関へ。女人結界門に6:30ごろ到着。門の「女」の文字が消されていました。レンゲ辻でもありましたが、結構いたずらされています。ここから山上ヶ岳を目指す。途中鍋担ぎ行者のお堂や、蛇腹をこえて、洞辻茶屋に8時についた。ここは茶屋があり、他の登山客や修験者がくつろいでいました。売店もありました。ここは携帯の電波が通じるようで、家に無事であることをメールで送信。ちなみにドコモとauのみです。

ここから先の行場の鐘掛岩など見たかったけど、積雪の影響で「通行止」になっていました。よって下山用の道を登ることに。この道は弥山や前鬼~太古の辻にある木製の階段があり、テント装備を詰め込んだバックパックが重く感じた。9時に「西の覗き」に到着。ここは荒行の場所で、岩の先端まで行って見ました。ほんとに断崖絶壁でちょこっと「くらっ」としました。ここから身を乗り出すなんて、身の縮む思いです。


宿坊をすぎ、10時ごろに大峯山寺につきました。以前行ったときは、門が閉ざされていましたが、今日は開いていました。中に入り祈りを奉げ、お土産に交通安全カーステッカーを購入。次の車につける予定 隣では、修験者が読経しておられました。ちなみに中は撮影禁止。よって外から撮影しました
隣では、修験者が読経しておられました。ちなみに中は撮影禁止。よって外から撮影しました

しばらくしてから、今日の宿泊地 小笹の宿を目指す。ところどころ残雪もありましたが(五番関~小笹の宿)、アイゼンをつける必要性はありませんでした。念のため携行しましたが、ただ重い思いをするだけでした
途中阿古滝分岐地点がありそこで休息。ただ滝へのルートは分かりづらい。目印のピンクテープはあるけど、違う方角にもあった。 立ち止まると見えてくるものもあって、大岩の上に立つ木や、若い芽が成長していたり新たな発見があります



11:30に小笹の宿に到着。早速テントをはる。テントを張り終えたら水汲みに。ここは避難小屋のそばを小川が流れていて水はたっぷりあります。浄水器「スーパーデリオス]を使って汲みました。私はそのままでは飲みません。綺麗に見えても、小さい砂や、細菌はすくなからず存在します。それに上に登山道があります。用を足している人がいないとも言えません。ですから浄水器は必携だと思います。
水を汲んでマルタイの棒ラーメンを食す。ジェットボイルは瞬間湯沸かし器みたいなものですが、爆沸っぽいので火力の微調整が必要。今回はちょっとふきこぼしてしまいました。
ハイライト前室をつけたハイライトはこんな感じです

これで快適性がグッとアップ! ただ広くするためにはしっかり固定してやる必要性があります。今回ペグが打てるだろうと思っていましたが、意外にも深く打ち込めなかった。なんとかペグで固定。細引きは5本持っていましたが、ペグを打てない状況を考えると前室を固定するのにあと2本くらい細引きは必要かな。前室は本体とはフックで連結します。ちゃんと本体の方に通すループがありました。あとポールにも1箇所固定します。前室にもしっかりベンチレーターがあり換気はよさそうです。



今日は私ともう一人若い男性だけ。小屋を利用する人はいません。この避難小屋ですが、中で火を起こした形跡があり煙臭かった。それにゴミが散乱・・・。登山者の良識を疑います。小屋は2,3人が横になれる程度です。きつきつなら5人。



この方たちが見ておられます。ゴミは持ち帰りましょう
夕飯は、豚角煮丼!登山雑誌でおいしそうだったから作ってみるとめちゃうま 甘辛いタレがご飯と絡み、角煮も柔らかくて絶品でした。角煮はトップバリューでお手ごろ価格で売られています
甘辛いタレがご飯と絡み、角煮も柔らかくて絶品でした。角煮はトップバリューでお手ごろ価格で売られています

角煮ですが、パック裏面に「高温多湿をさけ直射日光の当たらないところ」とあります。ということは常温OKなわけで登山にはもってこいです。ちなみに別のメーカーのものは10度以下とあります。注意して購入してください。あと、沸騰したお湯で暖め続けるのはNGらしく、パックが解けるらしい。私は沸騰させてから火を切り、パックを入れました。ジェットボイルはネオプレーンで容器の保温性がある程度あるので大丈夫です。 食事を終えると、夜中車で走り、寝不足のせいもあり、眠気が襲ってきました。19時ごろにシュラフに入りうとうとしていると眠りこけました。
以上1日目の投稿を終えます
ここから先の行場の鐘掛岩など見たかったけど、積雪の影響で「通行止」になっていました。よって下山用の道を登ることに。この道は弥山や前鬼~太古の辻にある木製の階段があり、テント装備を詰め込んだバックパックが重く感じた。9時に「西の覗き」に到着。ここは荒行の場所で、岩の先端まで行って見ました。ほんとに断崖絶壁でちょこっと「くらっ」としました。ここから身を乗り出すなんて、身の縮む思いです。
宿坊をすぎ、10時ごろに大峯山寺につきました。以前行ったときは、門が閉ざされていましたが、今日は開いていました。中に入り祈りを奉げ、お土産に交通安全カーステッカーを購入。次の車につける予定
 隣では、修験者が読経しておられました。ちなみに中は撮影禁止。よって外から撮影しました
隣では、修験者が読経しておられました。ちなみに中は撮影禁止。よって外から撮影しましたしばらくしてから、今日の宿泊地 小笹の宿を目指す。ところどころ残雪もありましたが(五番関~小笹の宿)、アイゼンをつける必要性はありませんでした。念のため携行しましたが、ただ重い思いをするだけでした

途中阿古滝分岐地点がありそこで休息。ただ滝へのルートは分かりづらい。目印のピンクテープはあるけど、違う方角にもあった。 立ち止まると見えてくるものもあって、大岩の上に立つ木や、若い芽が成長していたり新たな発見があります
11:30に小笹の宿に到着。早速テントをはる。テントを張り終えたら水汲みに。ここは避難小屋のそばを小川が流れていて水はたっぷりあります。浄水器「スーパーデリオス]を使って汲みました。私はそのままでは飲みません。綺麗に見えても、小さい砂や、細菌はすくなからず存在します。それに上に登山道があります。用を足している人がいないとも言えません。ですから浄水器は必携だと思います。
水を汲んでマルタイの棒ラーメンを食す。ジェットボイルは瞬間湯沸かし器みたいなものですが、爆沸っぽいので火力の微調整が必要。今回はちょっとふきこぼしてしまいました。
ハイライト前室をつけたハイライトはこんな感じです
これで快適性がグッとアップ! ただ広くするためにはしっかり固定してやる必要性があります。今回ペグが打てるだろうと思っていましたが、意外にも深く打ち込めなかった。なんとかペグで固定。細引きは5本持っていましたが、ペグを打てない状況を考えると前室を固定するのにあと2本くらい細引きは必要かな。前室は本体とはフックで連結します。ちゃんと本体の方に通すループがありました。あとポールにも1箇所固定します。前室にもしっかりベンチレーターがあり換気はよさそうです。
今日は私ともう一人若い男性だけ。小屋を利用する人はいません。この避難小屋ですが、中で火を起こした形跡があり煙臭かった。それにゴミが散乱・・・。登山者の良識を疑います。小屋は2,3人が横になれる程度です。きつきつなら5人。
この方たちが見ておられます。ゴミは持ち帰りましょう
夕飯は、豚角煮丼!登山雑誌でおいしそうだったから作ってみるとめちゃうま
 甘辛いタレがご飯と絡み、角煮も柔らかくて絶品でした。角煮はトップバリューでお手ごろ価格で売られています
甘辛いタレがご飯と絡み、角煮も柔らかくて絶品でした。角煮はトップバリューでお手ごろ価格で売られています角煮ですが、パック裏面に「高温多湿をさけ直射日光の当たらないところ」とあります。ということは常温OKなわけで登山にはもってこいです。ちなみに別のメーカーのものは10度以下とあります。注意して購入してください。あと、沸騰したお湯で暖め続けるのはNGらしく、パックが解けるらしい。私は沸騰させてから火を切り、パックを入れました。ジェットボイルはネオプレーンで容器の保温性がある程度あるので大丈夫です。 食事を終えると、夜中車で走り、寝不足のせいもあり、眠気が襲ってきました。19時ごろにシュラフに入りうとうとしていると眠りこけました。
以上1日目の投稿を終えます
2011年05月08日
ギアあれこれ
今回は登山用ギアを紹介しようと思います
まずはモンベル ルルイパック45
以前はフォトグラファー専用ザックを使用していましたが、重くてかさばることからこのザックを使用しています。スノーシューをくくりつけたり、スキー板を装着できたり便利です。もちろんカメラの三脚を固定するために使用しています。

ハイドレーションにも対応。年中使えるバックパックと思います。石鎚山へもこれでいきました。ただ、カメラなど重いものはバランスの関係上ザックの上のほうにパッキングしたいんだけどそんな仕切りはないのでそれが不便。すこし改善が必要。あといま使っているキャメルバッグとはフックの位置が違うのでこれも工夫しなくてはなりません。
帽子は3シーズンこれを使っています

エアモンテ、アドベンチャーハット です。この帽子はホーボージュンさんの実践主義道具学1?で紹介されていて、これだと思い購入。特徴はおおきなツバ。キャディーさんのような帽子でこれで直射日光を遮断していくれます。これがとてつもなく重要。以前、白山をキャップで縦走したとき顔の側面(頬)を日焼けで深刻にやられました。日焼けというより火傷に近い・・・。周囲から大丈夫?という目で見られました。また後頭部も日差しから守ってくれます。私は肌を焼きたくない派なので、おすすめです。 巷では日焼け止めクリームがありますが私はあれは使いたくありません。塗りたくないのと、説明書に衣服には絶対につけないことや汗で流れたら塗りなおしてくださいなどそんな面倒くさいことしたくありません。
今回の熊野古道とは別に次項で書きますが、つかってみたのがSOTO ポケトーチ!百円ライターが凄まじい火力の小型バーナーになります
 ストーブに点火するのもこれで楽々デス。ただ連続使用時間は1分強?だったかな。ウルトラマンのカラータイマーの3分の1しか持ちません。
ストーブに点火するのもこれで楽々デス。ただ連続使用時間は1分強?だったかな。ウルトラマンのカラータイマーの3分の1しか持ちません。
登山の食事ではいつもジェットボイルとスノーピーク チタンダブルマグ450を使用しています。
ジェットボイルは本当に便利ですぐに湯が沸きます。私は登山では手の込んだ料理はしません。湯を沸かし、アルファ米を戻して、レトルトなどを暖めて食べるのが私のパターン。理由は汚したくないから。汚すとそれを拭く為にキッチンペーパーを使用しますがこれが水分を含んで重くなりますし、ゴミが増えます。
チタンダブルマグ450は高価でしたが買っちまいました。やはりこれくらいの容量が必要だとおもいます。以前はチタンシングルマグ220を使用していましたが、卵スープや、具の多いスープを作るのには容量不足でした。これだと安心。それに2重構造なので保温性もあります。蓋も別に売られていて、保温性をあげたり、中身をこぼれにくくすることや、また壊れやすいもの(卵とか)を入れて破損しにくくしています。

画像は次回紹介しようと思う小笹の宿でのひと時です。以前紹介した山専用棒ラーメンマルタイを試食しました。醤油味で、麺は10%増量!ゴマ入りで、しかもなんとシジミがちゃんと入っています。これには驚き!すこし磯の香りします。ただ含有塩分量は5.8グラム?だったかな。登山では塩分補給のためには良いかもしれませが、普段の生活ではちょっと・・。
今回はこれくらい 次回は山上ヶ岳~稲村ヶ岳 の周遊を投稿したいと思います
こいつを実践投入しました

前室サイコーです やっぱ快適! ここの幕営地もすてきでした
やっぱし画像が変 申し訳ない
申し訳ない
あと、バディシステムを教えてくれた友人よ!ありがとう
まずはモンベル ルルイパック45
以前はフォトグラファー専用ザックを使用していましたが、重くてかさばることからこのザックを使用しています。スノーシューをくくりつけたり、スキー板を装着できたり便利です。もちろんカメラの三脚を固定するために使用しています。
ハイドレーションにも対応。年中使えるバックパックと思います。石鎚山へもこれでいきました。ただ、カメラなど重いものはバランスの関係上ザックの上のほうにパッキングしたいんだけどそんな仕切りはないのでそれが不便。すこし改善が必要。あといま使っているキャメルバッグとはフックの位置が違うのでこれも工夫しなくてはなりません。
帽子は3シーズンこれを使っています
エアモンテ、アドベンチャーハット です。この帽子はホーボージュンさんの実践主義道具学1?で紹介されていて、これだと思い購入。特徴はおおきなツバ。キャディーさんのような帽子でこれで直射日光を遮断していくれます。これがとてつもなく重要。以前、白山をキャップで縦走したとき顔の側面(頬)を日焼けで深刻にやられました。日焼けというより火傷に近い・・・。周囲から大丈夫?という目で見られました。また後頭部も日差しから守ってくれます。私は肌を焼きたくない派なので、おすすめです。 巷では日焼け止めクリームがありますが私はあれは使いたくありません。塗りたくないのと、説明書に衣服には絶対につけないことや汗で流れたら塗りなおしてくださいなどそんな面倒くさいことしたくありません。
今回の熊野古道とは別に次項で書きますが、つかってみたのがSOTO ポケトーチ!百円ライターが凄まじい火力の小型バーナーになります

登山の食事ではいつもジェットボイルとスノーピーク チタンダブルマグ450を使用しています。
ジェットボイルは本当に便利ですぐに湯が沸きます。私は登山では手の込んだ料理はしません。湯を沸かし、アルファ米を戻して、レトルトなどを暖めて食べるのが私のパターン。理由は汚したくないから。汚すとそれを拭く為にキッチンペーパーを使用しますがこれが水分を含んで重くなりますし、ゴミが増えます。
チタンダブルマグ450は高価でしたが買っちまいました。やはりこれくらいの容量が必要だとおもいます。以前はチタンシングルマグ220を使用していましたが、卵スープや、具の多いスープを作るのには容量不足でした。これだと安心。それに2重構造なので保温性もあります。蓋も別に売られていて、保温性をあげたり、中身をこぼれにくくすることや、また壊れやすいもの(卵とか)を入れて破損しにくくしています。
画像は次回紹介しようと思う小笹の宿でのひと時です。以前紹介した山専用棒ラーメンマルタイを試食しました。醤油味で、麺は10%増量!ゴマ入りで、しかもなんとシジミがちゃんと入っています。これには驚き!すこし磯の香りします。ただ含有塩分量は5.8グラム?だったかな。登山では塩分補給のためには良いかもしれませが、普段の生活ではちょっと・・。
今回はこれくらい 次回は山上ヶ岳~稲村ヶ岳 の周遊を投稿したいと思います
こいつを実践投入しました
前室サイコーです やっぱ快適! ここの幕営地もすてきでした
やっぱし画像が変
 申し訳ない
申し訳ないあと、バディシステムを教えてくれた友人よ!ありがとう

2011年05月07日
熊野古道 ツヅラト峠~荷坂峠
GWに熊野古道に行きました。どこが良いかと悩んだあげく、紀伊長島道の駅マンボウを起点にぐるっとまわれるのがいいことと、途中にJRの梅ヶ谷駅もあるので便利そうだったかです。
早朝道の駅を出発しました。ただ登山口まで長いこと歩かなければなりません。だいたい、1時間近く歩きました。途中で紀勢道の橋脚が作られているのが見えました。建設は着々と進んでいるようです。

ツヅラト峠登山口に到着し、ここから本番。始まってすぐに石畳を歩きます。馬越峠のように結構続くのかと思っていましたが、ここは短かったです。この峠での特徴は「野面乱層積み」でしょうか。石が幾重にも詰まれてその上が道になっています。これは確か築城のときもこのような方法があった気がします

登山口から1時間程度で頂上に到着しました。東屋があり、スタンプを押しました。ここから見晴台へ行き熊野灘を一望といいたいところですが、黄砂の影響で視界が悪い。海は見えるようで見えない

20分くらいのんびりし下山。大内山からの登り口へは20分くらいでいけた。ただここから42号線に出るまでが遠い。ひたすらアスファルト道を歩いたようなきがします。大内山で目をひいたのが、害獣対策用の電気柵?。一部だけと思っていましたが、これが広い範囲にめぐらしてあり驚きました。そんなにも、農作物への被害が深刻なのでしょうか?


歩いてようやく42号線に合流。これから荷坂峠へ向かいますが、これも登山口まで長かった。ひたすら42号線を南下し30分。登山口に到着。途中荷坂トンネルを横断しなくてはなりませんがこれが一番怖かった。GWで車が多くしかもみんな結構飛ばす!車の切れ目を走りました。荷坂峠では石畳はありませんでした。ここは42号線に近いため車の音や、JR紀勢線で列車の鉄橋を通過する音がこだまします。ここも展望台「沖見平」があり眺めが良いはずなんだけど、視界が悪く白くガスっています。ただ、ツツジは綺麗でした。

ここでもスタンプを押し、設置していあるノートに今日来たことを書いて、しばらく靴を脱いでベンチでのんびりしていました。 それから出発して30分くらいで道の駅マンボウに到着。昼とあってすごい車に人!ここで焼きさば寿司を買い、それとマンボウの串焼きを注文。マンボウの肉はコリコリしてて食感はよかったです。ただ、ちょっと塩コショウかけ過ぎ。1本350円だったかな。ここから、行ってみたかった秘湯「有久寺温泉」へ向かう。42号線から422号線へ。松原橋の手前に看板がありそこを右折。

そこから狭い道を走るとありました!山奥にひっそりと佇んでいます。700円を支払入浴。冷泉なので、最初ぬるかったが、ボイラーで暖めてくれたのか、だんたんあったまってきました。私一人のためにありがたいことです。温泉入り口、お風呂はこんな様子です


スーパー銭湯とは対極にある、開放的な温泉です 風呂は2,3人で一杯という広さ!しかも、換気扇がないのか水蒸気がものごく、薄暗いです。それでもここは魅力的です。あと、貴重品ロッカーというものは存在しませんので、私は防水パックに入れて風呂に持ち込みました。すっかり満喫し風呂から上がって、寺などをマミヤで撮影していると住職に記者に間違われました。ま、悪い気はしませんが。ここには黒のラブラドールがいて、かわいかった、ただ、人見知りする犬で、目をあわそうとしません。
風呂は2,3人で一杯という広さ!しかも、換気扇がないのか水蒸気がものごく、薄暗いです。それでもここは魅力的です。あと、貴重品ロッカーというものは存在しませんので、私は防水パックに入れて風呂に持ち込みました。すっかり満喫し風呂から上がって、寺などをマミヤで撮影していると住職に記者に間違われました。ま、悪い気はしませんが。ここには黒のラブラドールがいて、かわいかった、ただ、人見知りする犬で、目をあわそうとしません。
小1時間くらい滞在し帰路へ。いったん、尾鷲に行き名物「とら巻き」を買おうとしたけどすでに売り切れ。結構ショックを受ける。このままでは帰れないと思い「おとと」に行き、カワハギの干物などを買い
紀勢大内山インターへ。そしてここでも寄り道して、椎茸 の酒粕漬を買い帰りました。インター近くで面白い店を発見!釣り好きにはたまらないお店でしょう
の酒粕漬を買い帰りました。インター近くで面白い店を発見!釣り好きにはたまらないお店でしょう

跳ねるのは「馬」ではなく「海老」でした。しかも2匹 今回も画像がおかしくなり申し訳ございません
今回も画像がおかしくなり申し訳ございません
早朝道の駅を出発しました。ただ登山口まで長いこと歩かなければなりません。だいたい、1時間近く歩きました。途中で紀勢道の橋脚が作られているのが見えました。建設は着々と進んでいるようです。
ツヅラト峠登山口に到着し、ここから本番。始まってすぐに石畳を歩きます。馬越峠のように結構続くのかと思っていましたが、ここは短かったです。この峠での特徴は「野面乱層積み」でしょうか。石が幾重にも詰まれてその上が道になっています。これは確か築城のときもこのような方法があった気がします
登山口から1時間程度で頂上に到着しました。東屋があり、スタンプを押しました。ここから見晴台へ行き熊野灘を一望といいたいところですが、黄砂の影響で視界が悪い。海は見えるようで見えない

20分くらいのんびりし下山。大内山からの登り口へは20分くらいでいけた。ただここから42号線に出るまでが遠い。ひたすらアスファルト道を歩いたようなきがします。大内山で目をひいたのが、害獣対策用の電気柵?。一部だけと思っていましたが、これが広い範囲にめぐらしてあり驚きました。そんなにも、農作物への被害が深刻なのでしょうか?
歩いてようやく42号線に合流。これから荷坂峠へ向かいますが、これも登山口まで長かった。ひたすら42号線を南下し30分。登山口に到着。途中荷坂トンネルを横断しなくてはなりませんがこれが一番怖かった。GWで車が多くしかもみんな結構飛ばす!車の切れ目を走りました。荷坂峠では石畳はありませんでした。ここは42号線に近いため車の音や、JR紀勢線で列車の鉄橋を通過する音がこだまします。ここも展望台「沖見平」があり眺めが良いはずなんだけど、視界が悪く白くガスっています。ただ、ツツジは綺麗でした。
ここでもスタンプを押し、設置していあるノートに今日来たことを書いて、しばらく靴を脱いでベンチでのんびりしていました。 それから出発して30分くらいで道の駅マンボウに到着。昼とあってすごい車に人!ここで焼きさば寿司を買い、それとマンボウの串焼きを注文。マンボウの肉はコリコリしてて食感はよかったです。ただ、ちょっと塩コショウかけ過ぎ。1本350円だったかな。ここから、行ってみたかった秘湯「有久寺温泉」へ向かう。42号線から422号線へ。松原橋の手前に看板がありそこを右折。
そこから狭い道を走るとありました!山奥にひっそりと佇んでいます。700円を支払入浴。冷泉なので、最初ぬるかったが、ボイラーで暖めてくれたのか、だんたんあったまってきました。私一人のためにありがたいことです。温泉入り口、お風呂はこんな様子です
スーパー銭湯とは対極にある、開放的な温泉です
 風呂は2,3人で一杯という広さ!しかも、換気扇がないのか水蒸気がものごく、薄暗いです。それでもここは魅力的です。あと、貴重品ロッカーというものは存在しませんので、私は防水パックに入れて風呂に持ち込みました。すっかり満喫し風呂から上がって、寺などをマミヤで撮影していると住職に記者に間違われました。ま、悪い気はしませんが。ここには黒のラブラドールがいて、かわいかった、ただ、人見知りする犬で、目をあわそうとしません。
風呂は2,3人で一杯という広さ!しかも、換気扇がないのか水蒸気がものごく、薄暗いです。それでもここは魅力的です。あと、貴重品ロッカーというものは存在しませんので、私は防水パックに入れて風呂に持ち込みました。すっかり満喫し風呂から上がって、寺などをマミヤで撮影していると住職に記者に間違われました。ま、悪い気はしませんが。ここには黒のラブラドールがいて、かわいかった、ただ、人見知りする犬で、目をあわそうとしません。小1時間くらい滞在し帰路へ。いったん、尾鷲に行き名物「とら巻き」を買おうとしたけどすでに売り切れ。結構ショックを受ける。このままでは帰れないと思い「おとと」に行き、カワハギの干物などを買い
紀勢大内山インターへ。そしてここでも寄り道して、椎茸
 の酒粕漬を買い帰りました。インター近くで面白い店を発見!釣り好きにはたまらないお店でしょう
の酒粕漬を買い帰りました。インター近くで面白い店を発見!釣り好きにはたまらないお店でしょう跳ねるのは「馬」ではなく「海老」でした。しかも2匹
 今回も画像がおかしくなり申し訳ございません
今回も画像がおかしくなり申し訳ございません