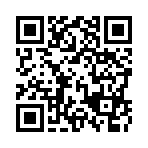2014年06月30日
台高山脈南部 尾鷲道 大台ケ原~コブシ嶺とトロッコ道跡を訪ねて
台高山脈南部の尾鷲道の尾鷲辻~コブシ嶺を歩いてきました。それとかつてのトロッコ道を探索。
大台ケ原駐車場を4時半に出発。天気はまずまずよさそうだ

尾鷲辻に5時に到着。さて、気を引き締めていきますか!

ルート自体は高低差はそんなになさそう。ただ、道迷いの可能性はありそうだ。テープや踏み跡がどれほどあるのかが気がかりでした。歩いてみて、前半は踏み跡やテープ類は結構あるほうだ。少し安心した。トラバース道をしばらくいくと、先の木に何やら赤いペンキがかかれていた

左に行くと堂倉山。右はコブシ嶺の分岐点のよう

矢印に従いコブシ嶺方面へ。その方向にあるテープを拾っていく。途中には沢もあったりと水の確保もできそうだ

6時過ぎに白サコ(標高1405.4)に到着。ここから大蛇嵓方面へのトロッコ道跡が微かにある・・・・。それは後程行くとしてまずはコブシ嶺を目指します。

ルートは稜線の西斜面のほとんどトラバース。ただ、斜面の崩壊している場所があるのでそこは迂回してすすみます
ここは、ザレて危険なので迂回します。踏み跡っぽいのはあるんだけどね・・・

コブシ嶺が視界に入りあと少し。しかし地倉山付近でテープをロスト。踏み跡もない。すこし迷った。ガーミンを起動し修正し地倉山へ到達

もうあとちょい!

周囲ではこの抜け殻の主であろう鳴き声がけたたましく鳴いている

雷峠を通過してコブシ嶺へ!7時半に到達。駐車場から3時間かかりました

前は海山から、今回は大台ケ原から これで南部は繋がった

三脚で記念撮影をしようとしたが、なぜか雲台を締めるネジがなくなっている・・・ 三脚はただの高い棒切れになりはてた・・・
三脚はただの高い棒切れになりはてた・・・

休憩しようとしたが、蠅?がよって鬱陶しい。そこそこに出発。さて戻りますか!

戻る途中で見つけた看板。ここが最高点?

アカヤシオもまだまだいける

不明

このときはまだ青空だった 清々しいですね

東ノ川・坂本貯水池方面の眺め

再び地倉山で道迷い 稜線に丁寧に沿って行こうとテープを拾っていたがなくなって、石楠花に阻まれる。あたりをウロチョロしまくった
稜線に丁寧に沿って行こうとテープを拾っていたがなくなって、石楠花に阻まれる。あたりをウロチョロしまくった
再び白サコに着いた。ここからトロッコ道跡に進路を変更。大蛇嵓南東の斜面を目指します
気になったきっかけは、「三重県の森林鉄道」という本

尾鷲から索道、インクライン、トロッコを使って、大台ケ原の原生林を切だしていたそうな。昔は林業はとても活気があったようですね。
それを見に別の日に大杉谷のトロッコ道跡やインクラインの谷 その名も「インクラ谷」、千尋滝上部の索道基部跡とか見たかったけど、林道「父ヶ谷線」は通行止 しかも現地は土砂降りで中止となりました

白サコ だいたいこんな感じかな・・・

トロ道跡の部分だけ木々なく開けて、フラットな感じ。軌道を敷設するのに、急勾配はそんなにないはず。
このような道が最初の方は続きます

人工的なもの 何の部品なんだろうか?

酒瓶や小皿、小さな瓶・・・・? 宴会?


しばらく行くと沢にあたる。 ここは石積みがしてあった

道はだんだん細く、斜面も急になっている。ガーミンで確認すると大蛇嵓(ハイキングコース終点)の南東部分にいるようだ。気を抜くと滑落する危険性も。もうやめにしようかと歩いていると、ネットの画像で見た岩の切り通し部分を発見 どうやらあっているようだ。再び隧道の期待が高まる。
どうやらあっているようだ。再び隧道の期待が高まる。

そしてようやく10時半ごろに隧道跡を発見しました。ふ~一安心

中は水没してるようだ

大蛇嵓の下を通り蒸篭嵓を掘って軌道を敷設しようと計画があったらしい。掘削跡が残っているようだが、不明。
「天空の城 ラピュタ」の鉱山都市の鉄道の感じのようになったのだろうか?そう考えると楽しいですね
ガーミンで現在地を確認。どうもハイキングコースの大蛇嵓分岐点の南斜面にいるようだ。山と高原地図25000分の1の シャクナゲの「ゲ」の字の部分。ここから直登して、ハイキングコースに合流します。本当はいけないのでしょうけど、また堂倉方面にもどるなんて絶対したくない・・・。ハイキングコースに出て、久しぶりに大蛇嵓へ
どうやってトロッコを走らせようとしたんかいな?こんな崖に・・・・

シオカラ谷で顔を洗い駐車場に戻ります。途中に西大台の利用調整の看板がありますが、ここもどうやら軌道がナゴヤ谷まであったようです

その手前のハイキングコース一部はトラバース道になっているからもとはここにトロッコが走っていたのかな?

いろんな想像を膨らませて駐車場に戻ってきました。天気はどんより・・・。平日なので車は少ないですね

後片付けをしていると、雨が当たってきました。帰り際でラッキーです 行動中に降られんでよかったわ
というわけで、中身の濃い尾鷲道とトロッコ道跡の探索になりました
霧雨の大台ケ原を後にします

大台ケ原駐車場を4時半に出発。天気はまずまずよさそうだ
尾鷲辻に5時に到着。さて、気を引き締めていきますか!
ルート自体は高低差はそんなになさそう。ただ、道迷いの可能性はありそうだ。テープや踏み跡がどれほどあるのかが気がかりでした。歩いてみて、前半は踏み跡やテープ類は結構あるほうだ。少し安心した。トラバース道をしばらくいくと、先の木に何やら赤いペンキがかかれていた
左に行くと堂倉山。右はコブシ嶺の分岐点のよう
矢印に従いコブシ嶺方面へ。その方向にあるテープを拾っていく。途中には沢もあったりと水の確保もできそうだ
6時過ぎに白サコ(標高1405.4)に到着。ここから大蛇嵓方面へのトロッコ道跡が微かにある・・・・。それは後程行くとしてまずはコブシ嶺を目指します。
ルートは稜線の西斜面のほとんどトラバース。ただ、斜面の崩壊している場所があるのでそこは迂回してすすみます
ここは、ザレて危険なので迂回します。踏み跡っぽいのはあるんだけどね・・・
コブシ嶺が視界に入りあと少し。しかし地倉山付近でテープをロスト。踏み跡もない。すこし迷った。ガーミンを起動し修正し地倉山へ到達
もうあとちょい!
周囲ではこの抜け殻の主であろう鳴き声がけたたましく鳴いている
雷峠を通過してコブシ嶺へ!7時半に到達。駐車場から3時間かかりました
前は海山から、今回は大台ケ原から これで南部は繋がった
三脚で記念撮影をしようとしたが、なぜか雲台を締めるネジがなくなっている・・・
 三脚はただの高い棒切れになりはてた・・・
三脚はただの高い棒切れになりはてた・・・ 休憩しようとしたが、蠅?がよって鬱陶しい。そこそこに出発。さて戻りますか!
戻る途中で見つけた看板。ここが最高点?
アカヤシオもまだまだいける
不明
このときはまだ青空だった 清々しいですね
東ノ川・坂本貯水池方面の眺め
再び地倉山で道迷い
 稜線に丁寧に沿って行こうとテープを拾っていたがなくなって、石楠花に阻まれる。あたりをウロチョロしまくった
稜線に丁寧に沿って行こうとテープを拾っていたがなくなって、石楠花に阻まれる。あたりをウロチョロしまくった再び白サコに着いた。ここからトロッコ道跡に進路を変更。大蛇嵓南東の斜面を目指します
気になったきっかけは、「三重県の森林鉄道」という本
尾鷲から索道、インクライン、トロッコを使って、大台ケ原の原生林を切だしていたそうな。昔は林業はとても活気があったようですね。
それを見に別の日に大杉谷のトロッコ道跡やインクラインの谷 その名も「インクラ谷」、千尋滝上部の索道基部跡とか見たかったけど、林道「父ヶ谷線」は通行止 しかも現地は土砂降りで中止となりました
白サコ だいたいこんな感じかな・・・

トロ道跡の部分だけ木々なく開けて、フラットな感じ。軌道を敷設するのに、急勾配はそんなにないはず。
このような道が最初の方は続きます
人工的なもの 何の部品なんだろうか?
酒瓶や小皿、小さな瓶・・・・? 宴会?
しばらく行くと沢にあたる。 ここは石積みがしてあった
道はだんだん細く、斜面も急になっている。ガーミンで確認すると大蛇嵓(ハイキングコース終点)の南東部分にいるようだ。気を抜くと滑落する危険性も。もうやめにしようかと歩いていると、ネットの画像で見た岩の切り通し部分を発見
 どうやらあっているようだ。再び隧道の期待が高まる。
どうやらあっているようだ。再び隧道の期待が高まる。そしてようやく10時半ごろに隧道跡を発見しました。ふ~一安心
中は水没してるようだ
大蛇嵓の下を通り蒸篭嵓を掘って軌道を敷設しようと計画があったらしい。掘削跡が残っているようだが、不明。
「天空の城 ラピュタ」の鉱山都市の鉄道の感じのようになったのだろうか?そう考えると楽しいですね
ガーミンで現在地を確認。どうもハイキングコースの大蛇嵓分岐点の南斜面にいるようだ。山と高原地図25000分の1の シャクナゲの「ゲ」の字の部分。ここから直登して、ハイキングコースに合流します。本当はいけないのでしょうけど、また堂倉方面にもどるなんて絶対したくない・・・。ハイキングコースに出て、久しぶりに大蛇嵓へ
どうやってトロッコを走らせようとしたんかいな?こんな崖に・・・・
シオカラ谷で顔を洗い駐車場に戻ります。途中に西大台の利用調整の看板がありますが、ここもどうやら軌道がナゴヤ谷まであったようです
その手前のハイキングコース一部はトラバース道になっているからもとはここにトロッコが走っていたのかな?
いろんな想像を膨らませて駐車場に戻ってきました。天気はどんより・・・。平日なので車は少ないですね
後片付けをしていると、雨が当たってきました。帰り際でラッキーです 行動中に降られんでよかったわ

というわけで、中身の濃い尾鷲道とトロッコ道跡の探索になりました
霧雨の大台ケ原を後にします
2014年06月16日
和佐又ヒュッテ~大普賢岳~七曜岳 周遊と天女の花
久しぶりの大峯。カモシカさんのブログによると、大峯の天女の花「オオヤマレンゲ」が見ごろのよう。いままで、まったく見たことが無かったので、梅雨の晴れ間に行ってきました(6月16日)。
4時半位にヒュッテに到着。オオヤマレンゲはどこだと探すとヒュッテの入り口前にありました うむ、いままでぜんぜん気が付かなかったです。和佐又山への登り口にもありますね。つぼみ、花真っ盛りのもの、枯れているものまで、今週までが見ごろのようですね
うむ、いままでぜんぜん気が付かなかったです。和佐又山への登り口にもありますね。つぼみ、花真っ盛りのもの、枯れているものまで、今週までが見ごろのようですね


登る前に少し撮影しました。5時に登山開始。久々の周遊です
朝は気温が低くて歩いて気持ちが良い。大台ケ原ドライブウェーから日の出を迎えた

新緑の森の中を歩きます。

窟の役行者を拝み・・・

梯子場ではこの時期いつも定位置にコイワカガミが咲いている。可憐でちんまりした花ですね

何度も梯子を上がって行きます。このルートは険しい

シャクナゲがぎりぎり咲いていた。ラッキー

大普賢岳に近づくにつれ、シロヤシオが咲き乱れていた。大普賢岳の頂上や七曜岳までのトレールでもたくさん。今年は当たり年なのでしょうか?
大普賢岳より八経ヶ岳方面を

少しピンクがかっているものも

シロヤシオのフラワーロードぽかったです

シロヤシオを愛でるのは鎖場手前まで。ここから気を引き締めていきます。
大普賢岳や小普賢岳の急峻な山容がかっこええ

鎖場でなぜか「ヒルさがりのジョニー」がこの状態で! ゲットだぜ!中身もばっちり! ここらへんでもヒルはいるのか?

鎖場を登って9時ごろに「七曜岳」に到着。ここは狭いし座りにくいので、先の分岐点まで行き、そこで休憩しました。ここから先、無双洞まで激下り。靴の紐をきつく締め直して下って行きます。
木の根が絡んで下りにくい・・・ そしてつまづく!トレッキングポール先端が挟まってしまう!

無双洞までの下りで見つけた巨木

無双洞に10時半過ぎに到着。ヒュッテから左回りだと、ここはとてもありがた~い水場になります。浄水器で水を濾過し水分を補給。(取り過ぎに注意)
無双洞には木の梯子がなかった。流されたのだろうか?穴から冷たいが止めどなく溢れてきますね。顔を洗うと気持ちいいですよ

その下にある「水簾の滝」 マイナスイオンたっぷりでございます

癒しをたっぷりもらい、これから、岩登りの場所へ。激下りに膝が笑っている状態でこの登りはさぞかし堪えることでしょう。私は大丈夫ですよ
三点確保で確実に登って行きます。鎖もロープもつけてもらってあるのでそれを補助としてゆっくり進めば問題ないと思います。

ここを攻略すると、あとは緩やかに登るトラバース道。巨木があったりときれいな森の中を通って行きます
アンダーが強すぎた・・・


食べれそうなキノコ。だが触れるとキノコの傘の裏側から虫がいっぱい出てきた 興味本位で触らんかったらよかった
興味本位で触らんかったらよかった

13時にヒュッテに戻ってきました。荷物を車に詰め込んで、また天女の花を見に行きます。
ヒュッテのこの一部だけなんでしょうかね? あとは八経ヶ岳付近なのだろうか?

以上、ひさびさの大峯のレポートでした
4時半位にヒュッテに到着。オオヤマレンゲはどこだと探すとヒュッテの入り口前にありました
 うむ、いままでぜんぜん気が付かなかったです。和佐又山への登り口にもありますね。つぼみ、花真っ盛りのもの、枯れているものまで、今週までが見ごろのようですね
うむ、いままでぜんぜん気が付かなかったです。和佐又山への登り口にもありますね。つぼみ、花真っ盛りのもの、枯れているものまで、今週までが見ごろのようですね登る前に少し撮影しました。5時に登山開始。久々の周遊です
朝は気温が低くて歩いて気持ちが良い。大台ケ原ドライブウェーから日の出を迎えた
新緑の森の中を歩きます。
窟の役行者を拝み・・・
梯子場ではこの時期いつも定位置にコイワカガミが咲いている。可憐でちんまりした花ですね
何度も梯子を上がって行きます。このルートは険しい
シャクナゲがぎりぎり咲いていた。ラッキー
大普賢岳に近づくにつれ、シロヤシオが咲き乱れていた。大普賢岳の頂上や七曜岳までのトレールでもたくさん。今年は当たり年なのでしょうか?
大普賢岳より八経ヶ岳方面を
少しピンクがかっているものも
シロヤシオのフラワーロードぽかったです

シロヤシオを愛でるのは鎖場手前まで。ここから気を引き締めていきます。
大普賢岳や小普賢岳の急峻な山容がかっこええ
鎖場でなぜか「ヒルさがりのジョニー」がこの状態で! ゲットだぜ!中身もばっちり! ここらへんでもヒルはいるのか?
鎖場を登って9時ごろに「七曜岳」に到着。ここは狭いし座りにくいので、先の分岐点まで行き、そこで休憩しました。ここから先、無双洞まで激下り。靴の紐をきつく締め直して下って行きます。
木の根が絡んで下りにくい・・・ そしてつまづく!トレッキングポール先端が挟まってしまう!
無双洞までの下りで見つけた巨木
無双洞に10時半過ぎに到着。ヒュッテから左回りだと、ここはとてもありがた~い水場になります。浄水器で水を濾過し水分を補給。(取り過ぎに注意)
無双洞には木の梯子がなかった。流されたのだろうか?穴から冷たいが止めどなく溢れてきますね。顔を洗うと気持ちいいですよ
その下にある「水簾の滝」 マイナスイオンたっぷりでございます
癒しをたっぷりもらい、これから、岩登りの場所へ。激下りに膝が笑っている状態でこの登りはさぞかし堪えることでしょう。私は大丈夫ですよ

三点確保で確実に登って行きます。鎖もロープもつけてもらってあるのでそれを補助としてゆっくり進めば問題ないと思います。
ここを攻略すると、あとは緩やかに登るトラバース道。巨木があったりときれいな森の中を通って行きます
アンダーが強すぎた・・・
食べれそうなキノコ。だが触れるとキノコの傘の裏側から虫がいっぱい出てきた
 興味本位で触らんかったらよかった
興味本位で触らんかったらよかった13時にヒュッテに戻ってきました。荷物を車に詰め込んで、また天女の花を見に行きます。
ヒュッテのこの一部だけなんでしょうかね? あとは八経ヶ岳付近なのだろうか?
以上、ひさびさの大峯のレポートでした
2014年06月02日
台高山脈南部 尾鷲道 林道「栃山木組線」~コブシ嶺
台高山脈 北部の高見山や明神平、大台ケ原などは結構行っていますが、まったくノータッチの南部を行ってみたくなりました。大台ケ原から尾鷲方面への縦走路がありますが、今回は南部の海山からコブシ嶺を目指すことにしました。
道の駅海山から海山のキャンプ場への県道を行き「林道 栃山木組線」を進みます

帰りに撮影

最初は狭いアスファルト道だったけど進むにつれてダートに変わる。ガードレールがあると安心だが無いところもあり、ゆっくり進む。途中にひらけた場所があり、そこで朝を迎えた

落石多数の場所を慎重に

林道終点にはゲートがあり一般車両はここまでのよう。

支度を整えて5時半ごろ出発。ゲートの脇をすり抜けて林道を歩いて取りつき地点の地蔵峠を目指します
落石だらけの道。大きな岩がごろごろ 。林道は高度を上げながら続いています。林道の側に白い道標があり、ここが地蔵峠のようだ 5:49

木の梯子を登って尾根に取りつきます。ロープがあったのでありがたく使用させていただく。テープなどもあり安心

しばらく行くと、道標が
古和谷(尾鷲道)と「木組-神名水」方面分岐。 大台ケ原 「尾鷲道」は古和谷方面のようだ。
尾鷲道の看板が新しい。最近つけられたのだろうか?

ここから台高山脈の主稜線へ向かう。再び分岐点「又口辻」に到着 「神名水経由木組峠」と「山賊小屋」方面。行きは主稜線に突き進む計画なのでまっすぐ行きました
ピンクの矢印に向かっていきました

途中の開けたところからの山並が美しい。晴れだが視界があまり良くないのが残念だ

台高主稜線にぶつかり、「滝辻(標高1260M)」に着いた。6:45

ここから北へ稜線上を歩く。テープはわずかにある。踏み跡はほとんどなし。地形図とGPSフル活用し歩きました
途中にある大きな木を通過し・・・

三角点のある「中の嶺」に到着。しかし木々に遮られて視界は悪い。

ただシロヤシオは綺麗です。まだ見れました

中の嶺から新木組峠へ向かうルートが見つからず右往左往する。テープがどこかにないか?うろちょろして目を凝らすとテープ発見 ふ~ 一安心 これで進める。
ふ~ 一安心 これで進める。
稜線は木々に囲まれて視界は悪いと思っていたら、開けた場所に出た。これから行く台高主稜線を確認できた
遥か彼方に大台ケ原 奥に見える真っ平らな場所がそうかな?

稜線を進んでいく。登るところから、木々に糸を垂らしてぶら下がっているシャクトリムシのような幼虫(毛虫も)が鬱陶しい。トレッキングポールで薙ぎ払いながら進みます。GPSで現在地を確認し、新木組峠の場所に近づいていることが分かった。ここから帰りの「又口辻」方面への分岐の確認をやっておきたい。あたりを見回して歩き白い道標発見~! 「新木組峠」に到着しました 7:30頃
「新」はあとから付け足したような感じだな・・・

さて、選択肢が二つ。 トラバース道か尾根道か・・・ 尾根はアップダウンがありきつい。巻道は楽だが「崩落」Xとある。私はリスクがあるが楽なトラバース道を選びました。

ここから西側の斜面のトラバース道で楽ちん。いいペースで歩ける。崩落はどれくらいだろうと思っていると早くに出くわした。幅が10メートルくらいの崩落地。
ゆっくり慎重に進むが、バラバラと小石が下へ落ちていく。滑りやすくて滑落に注意が必要。なるべく下を見ないようにしました。

崩落個所は3か所あり、2か所は通過できましたが、最後はとても無理。ですので迂回して一旦尾根を目指す。
V字に崩落している。崩落場所に降りて登れるか試みるも土が柔らかすぎてボロボロ崩れてとても無理でした

迂回して歩いていると、看板発見。 と、ここが木組峠でした

コンパスで北を確認し、尾根道を行きます。目印は微かにある。 再びトラバース道の目印を発見。こっちに流れる

ただ、分かりにくいところは、自分でもってきたピンクテープを付けました。これで帰り道、迷うことがずっと少なくなると思う。また、来ると思うし

一本木を通過。

赤〇がしっかりあるところも

道幅が広く気持ちの良い トレール 明瞭なところは本当に明瞭 しっかりした道です

目指す「コブシ嶺」が見えてきた。あと少し

コブシ嶺への最後の登りにあえぎながら9時半過ぎに到着しました。

大峯方面の山並が綺麗です


景色を堪能し、行動食を取ります。ただ暑くてキャメルバックのスポーツドリンクを結構飲んでいて、リザーバーを確認してみるとあと700mlくらい。これから気温が上がりもっと暑くなるが、節約していかなければ。できれば神名水で水を補給できればと淡い期待を抱く。
10時に撤退 来た尾根を戻ります

ふたたび新木組峠に11時に到着。又口辻へのトラバース道を行く。道はしっかりしており、歩きやすいほう。30分くらいで神名水のところへ。

ただ、水は容器にすぐに汲めるほどの量がない 。岩の表面をチョロチョロつたっているくらいの水量。 浄水器「デリオス」の口を無理やり押し付けて一回につき50ミリリットルくらい汲めるのがやっとだったが、それを何回か繰り返し、喉を潤した。喉が渇いているときの水ほどおいしいものはありません。
。岩の表面をチョロチョロつたっているくらいの水量。 浄水器「デリオス」の口を無理やり押し付けて一回につき50ミリリットルくらい汲めるのがやっとだったが、それを何回か繰り返し、喉を潤した。喉が渇いているときの水ほどおいしいものはありません。
フィルター部分は外してマヨネーズの容器の口の部分をぐっと押しつけます。

木の橋が新しかったり

石を積んで道を作っていたりと、手の加えられているトラバース道でした

又口辻を正午ごろ通過し地蔵峠に12時半に戻ってきました。ここから再び林道をてくてく歩きます

13時にゲートへ。 車は無事でしたが、イモ虫の出す糸で汚くなってた・・・・
帰り支度をして出発。林道では 林業の方が木の切り出し作業をしていました。カニの爪のようなアームのショベルカーをすこし移動させてくださいました。お仕事中、邪魔してすんません。林道から県道へでます。魚跳渓の水の透明度は素晴らしい。暑いのでここで泳いでみたくなりますね。
吊り橋から撮影

滑らかに削られた岩壁。自然が作り出す造形は素晴らしいです

帰りに紀伊長島の「古里おんせん」に立ち寄り疲れを癒します。

最後に〆として「大内山牛乳」のソフトを食べて今回の尾鷲道のリポート終了です
濃厚だけどすっきりした後味の甘さなんですよ! 紀勢自動車道 奥伊勢PAにて販売中

伊勢茶ソフトもあるでよ! ただミックス頼んだら売り切れてた・・・
道の駅海山から海山のキャンプ場への県道を行き「林道 栃山木組線」を進みます
帰りに撮影
最初は狭いアスファルト道だったけど進むにつれてダートに変わる。ガードレールがあると安心だが無いところもあり、ゆっくり進む。途中にひらけた場所があり、そこで朝を迎えた
落石多数の場所を慎重に
林道終点にはゲートがあり一般車両はここまでのよう。
支度を整えて5時半ごろ出発。ゲートの脇をすり抜けて林道を歩いて取りつき地点の地蔵峠を目指します
落石だらけの道。大きな岩がごろごろ 。林道は高度を上げながら続いています。林道の側に白い道標があり、ここが地蔵峠のようだ 5:49
木の梯子を登って尾根に取りつきます。ロープがあったのでありがたく使用させていただく。テープなどもあり安心
しばらく行くと、道標が
古和谷(尾鷲道)と「木組-神名水」方面分岐。 大台ケ原 「尾鷲道」は古和谷方面のようだ。
尾鷲道の看板が新しい。最近つけられたのだろうか?
ここから台高山脈の主稜線へ向かう。再び分岐点「又口辻」に到着 「神名水経由木組峠」と「山賊小屋」方面。行きは主稜線に突き進む計画なのでまっすぐ行きました
ピンクの矢印に向かっていきました
途中の開けたところからの山並が美しい。晴れだが視界があまり良くないのが残念だ
台高主稜線にぶつかり、「滝辻(標高1260M)」に着いた。6:45
ここから北へ稜線上を歩く。テープはわずかにある。踏み跡はほとんどなし。地形図とGPSフル活用し歩きました
途中にある大きな木を通過し・・・
三角点のある「中の嶺」に到着。しかし木々に遮られて視界は悪い。
ただシロヤシオは綺麗です。まだ見れました
中の嶺から新木組峠へ向かうルートが見つからず右往左往する。テープがどこかにないか?うろちょろして目を凝らすとテープ発見
 ふ~ 一安心 これで進める。
ふ~ 一安心 これで進める。稜線は木々に囲まれて視界は悪いと思っていたら、開けた場所に出た。これから行く台高主稜線を確認できた
遥か彼方に大台ケ原 奥に見える真っ平らな場所がそうかな?
稜線を進んでいく。登るところから、木々に糸を垂らしてぶら下がっているシャクトリムシのような幼虫(毛虫も)が鬱陶しい。トレッキングポールで薙ぎ払いながら進みます。GPSで現在地を確認し、新木組峠の場所に近づいていることが分かった。ここから帰りの「又口辻」方面への分岐の確認をやっておきたい。あたりを見回して歩き白い道標発見~! 「新木組峠」に到着しました 7:30頃
「新」はあとから付け足したような感じだな・・・
さて、選択肢が二つ。 トラバース道か尾根道か・・・ 尾根はアップダウンがありきつい。巻道は楽だが「崩落」Xとある。私はリスクがあるが楽なトラバース道を選びました。
ここから西側の斜面のトラバース道で楽ちん。いいペースで歩ける。崩落はどれくらいだろうと思っていると早くに出くわした。幅が10メートルくらいの崩落地。
ゆっくり慎重に進むが、バラバラと小石が下へ落ちていく。滑りやすくて滑落に注意が必要。なるべく下を見ないようにしました。
崩落個所は3か所あり、2か所は通過できましたが、最後はとても無理。ですので迂回して一旦尾根を目指す。
V字に崩落している。崩落場所に降りて登れるか試みるも土が柔らかすぎてボロボロ崩れてとても無理でした
迂回して歩いていると、看板発見。 と、ここが木組峠でした
コンパスで北を確認し、尾根道を行きます。目印は微かにある。 再びトラバース道の目印を発見。こっちに流れる
ただ、分かりにくいところは、自分でもってきたピンクテープを付けました。これで帰り道、迷うことがずっと少なくなると思う。また、来ると思うし
一本木を通過。
赤〇がしっかりあるところも
道幅が広く気持ちの良い トレール 明瞭なところは本当に明瞭 しっかりした道です
目指す「コブシ嶺」が見えてきた。あと少し
コブシ嶺への最後の登りにあえぎながら9時半過ぎに到着しました。
大峯方面の山並が綺麗です
景色を堪能し、行動食を取ります。ただ暑くてキャメルバックのスポーツドリンクを結構飲んでいて、リザーバーを確認してみるとあと700mlくらい。これから気温が上がりもっと暑くなるが、節約していかなければ。できれば神名水で水を補給できればと淡い期待を抱く。
10時に撤退 来た尾根を戻ります
ふたたび新木組峠に11時に到着。又口辻へのトラバース道を行く。道はしっかりしており、歩きやすいほう。30分くらいで神名水のところへ。
ただ、水は容器にすぐに汲めるほどの量がない
 。岩の表面をチョロチョロつたっているくらいの水量。 浄水器「デリオス」の口を無理やり押し付けて一回につき50ミリリットルくらい汲めるのがやっとだったが、それを何回か繰り返し、喉を潤した。喉が渇いているときの水ほどおいしいものはありません。
。岩の表面をチョロチョロつたっているくらいの水量。 浄水器「デリオス」の口を無理やり押し付けて一回につき50ミリリットルくらい汲めるのがやっとだったが、それを何回か繰り返し、喉を潤した。喉が渇いているときの水ほどおいしいものはありません。 フィルター部分は外してマヨネーズの容器の口の部分をぐっと押しつけます。
木の橋が新しかったり
石を積んで道を作っていたりと、手の加えられているトラバース道でした
又口辻を正午ごろ通過し地蔵峠に12時半に戻ってきました。ここから再び林道をてくてく歩きます
13時にゲートへ。 車は無事でしたが、イモ虫の出す糸で汚くなってた・・・・
帰り支度をして出発。林道では 林業の方が木の切り出し作業をしていました。カニの爪のようなアームのショベルカーをすこし移動させてくださいました。お仕事中、邪魔してすんません。林道から県道へでます。魚跳渓の水の透明度は素晴らしい。暑いのでここで泳いでみたくなりますね。
吊り橋から撮影
滑らかに削られた岩壁。自然が作り出す造形は素晴らしいです
帰りに紀伊長島の「古里おんせん」に立ち寄り疲れを癒します。
最後に〆として「大内山牛乳」のソフトを食べて今回の尾鷲道のリポート終了です
濃厚だけどすっきりした後味の甘さなんですよ! 紀勢自動車道 奥伊勢PAにて販売中
伊勢茶ソフトもあるでよ! ただミックス頼んだら売り切れてた・・・