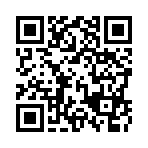2015年05月24日
古座川峡 巨岩・奇岩めぐり
望楼の芝で朝を迎えます。朝食のリフィルのために湯を沸かす。朝ラーメンをしてテントを撤収。ここから古座川の一枚岩を目指しました。
潮岬は左回りでドライブしているので、くしもと大橋を見やりながら、国道371号線を北上する

海岸線からすこし内陸に入っただけで、潮の気配は消えて鬱蒼とした森の中へ入り込んだような感じを受ける。海から山へ一気に変化する面白いところですね
一枚岩の道の駅に5時半ごろ到着した。今日は「嶽の森山」へまず登ります。
一枚岩はとてつもなく巨大ですね。道の駅ではカメラのファインダーに収まりません。山を一刀両断したような見事にスパッと切ったようなカタチですね。高さは100M、幅は500Mあるらしい 古座川もきれいな清流ですね。 ここでテント泊して、暑い日に清流に身を浸してみたいですね

国道371号線を一枚岩トンネル手前まで歩いて、そこを右折します 右に曲がったすぐそこが登山口になっていました(案内板あり)

「蜂に注意」の看板にびくつきながら落ち葉の多い登山道を登って行きます。
あれが目指す巨岩なんだろうか?

低山でもここはかなりスリルのあるところですね。 慎重に行きます。昨日のハードなトレランで筋肉痛を引きずっております。体があまり冴えない

道中はしっかり看板があり迷うことはないだろうと思います。ナメトコの手前の雰囲気のいい苔岩

ここの上部にネットで見た「ナメトコ岩」がありました。その沢の水たまりに「アカハライモリ?」が多数群れていましたよ

ナメトコ岩 ステップが切ってあるんですね ここ、大雨とかになったらどうなるんだろう

大雨の後はウォータースライダーかな 非常にキケンだろうけど・・・

ナメトコ上部まで登りきりそこから、ロープの垂れているところを登ります。幅の狭いところを行き、そこからさらに急登。

分岐点を左に行き、心もとない岩場のトラロープ。 頼りにせず3点確保で確実に

嶽の森山 「雄岳」に到着 遠くに海が見えるんですね。

次にいく「雌岳」を確認。一旦下り、登り返すのだろう

雄岳から少し激下りです。その途中蛇が尻尾を振って、私を歓迎(威嚇)している。あぶねえ・・・注意して歩きましょう
雌岳へも急な登り。木の枝をつかみながら、しっかり登って行きます。そしてついに雌岳へ。祠がありなかに石?が二つありました。
ここから見える「雄岳」はなかなか良いカタチしてマス

景色を十分堪能して下山することに。雌岳看板付近に踏み跡らしきものがあったけどこれはどこへいくのだろう・・・。薄いのでバリエーションかな?

下山ルートは雄岳と雌岳の鞍部にあるらしいが、行きは気付けなかった。注意深く見ると薄暗い急なところにロープがつけられていた。一枚岩への看板とかは鞍部にはなかった

少し下ると道案内の看板を発見

巨岩の下の巻道をくだりながらいきます。このルートは九十九折になっており、歩きやすいので周遊するなら下りにとったほうがいいと思う

途中にある「豆腐岩」と呼ばれるもの。豆腐でも高野豆腐だよな。 四角いブロックが積んであるみたい

相瀬橋付近の登山口にでた。3時間の行程でした

道の駅に戻り、特産の柚子を使ったドレッシングを購入 登山はこれで終了し、ここからドライブ。
古座川から天に向かって聳える「天柱岩」

滝の拝の渓流瀑 石が岩石を削って深い穴を創る(ポットホール) 一部が水路になってここで鮎を捕まえているのは有名ですね。映像と実際見るのとではこれが大違いで、ここは来てよかった!ただ道の駅はまだ営業時間前だった。
名勝・天然記念物であります

なめらか~に削られて

落差8Mの滝になる 右に階段状になっているのもあるんですね 決死の川遊びになりそう・・・ 地元の方はどうやって川遊びしてるのかな?

虫喰岩 結構大きい 道路を挟んだ反対側に道の駅あります

風雨によって浸食されできた穴・穴・穴 ホットケーキ焼くとこんなぶつぶつの穴ができるんだけどそれに似ていると自分は思う


上を見ると障子? だれか住んでたのかな?祠? どうやって運んだのだろう?

以上古座川峡での巖の巡礼でした とてもいいところですよ
潮岬は左回りでドライブしているので、くしもと大橋を見やりながら、国道371号線を北上する
海岸線からすこし内陸に入っただけで、潮の気配は消えて鬱蒼とした森の中へ入り込んだような感じを受ける。海から山へ一気に変化する面白いところですね

一枚岩の道の駅に5時半ごろ到着した。今日は「嶽の森山」へまず登ります。
一枚岩はとてつもなく巨大ですね。道の駅ではカメラのファインダーに収まりません。山を一刀両断したような見事にスパッと切ったようなカタチですね。高さは100M、幅は500Mあるらしい 古座川もきれいな清流ですね。 ここでテント泊して、暑い日に清流に身を浸してみたいですね
国道371号線を一枚岩トンネル手前まで歩いて、そこを右折します 右に曲がったすぐそこが登山口になっていました(案内板あり)
「蜂に注意」の看板にびくつきながら落ち葉の多い登山道を登って行きます。
あれが目指す巨岩なんだろうか?
低山でもここはかなりスリルのあるところですね。 慎重に行きます。昨日のハードなトレランで筋肉痛を引きずっております。体があまり冴えない

道中はしっかり看板があり迷うことはないだろうと思います。ナメトコの手前の雰囲気のいい苔岩
ここの上部にネットで見た「ナメトコ岩」がありました。その沢の水たまりに「アカハライモリ?」が多数群れていましたよ
ナメトコ岩 ステップが切ってあるんですね ここ、大雨とかになったらどうなるんだろう
大雨の後はウォータースライダーかな 非常にキケンだろうけど・・・
ナメトコ上部まで登りきりそこから、ロープの垂れているところを登ります。幅の狭いところを行き、そこからさらに急登。
分岐点を左に行き、心もとない岩場のトラロープ。 頼りにせず3点確保で確実に
嶽の森山 「雄岳」に到着 遠くに海が見えるんですね。
次にいく「雌岳」を確認。一旦下り、登り返すのだろう
雄岳から少し激下りです。その途中蛇が尻尾を振って、私を歓迎(威嚇)している。あぶねえ・・・注意して歩きましょう
雌岳へも急な登り。木の枝をつかみながら、しっかり登って行きます。そしてついに雌岳へ。祠がありなかに石?が二つありました。
ここから見える「雄岳」はなかなか良いカタチしてマス
景色を十分堪能して下山することに。雌岳看板付近に踏み跡らしきものがあったけどこれはどこへいくのだろう・・・。薄いのでバリエーションかな?
下山ルートは雄岳と雌岳の鞍部にあるらしいが、行きは気付けなかった。注意深く見ると薄暗い急なところにロープがつけられていた。一枚岩への看板とかは鞍部にはなかった
少し下ると道案内の看板を発見
巨岩の下の巻道をくだりながらいきます。このルートは九十九折になっており、歩きやすいので周遊するなら下りにとったほうがいいと思う
途中にある「豆腐岩」と呼ばれるもの。豆腐でも高野豆腐だよな。 四角いブロックが積んであるみたい
相瀬橋付近の登山口にでた。3時間の行程でした
道の駅に戻り、特産の柚子を使ったドレッシングを購入 登山はこれで終了し、ここからドライブ。
古座川から天に向かって聳える「天柱岩」
滝の拝の渓流瀑 石が岩石を削って深い穴を創る(ポットホール) 一部が水路になってここで鮎を捕まえているのは有名ですね。映像と実際見るのとではこれが大違いで、ここは来てよかった!ただ道の駅はまだ営業時間前だった。
名勝・天然記念物であります
なめらか~に削られて
落差8Mの滝になる 右に階段状になっているのもあるんですね 決死の川遊びになりそう・・・ 地元の方はどうやって川遊びしてるのかな?
虫喰岩 結構大きい 道路を挟んだ反対側に道の駅あります
風雨によって浸食されできた穴・穴・穴 ホットケーキ焼くとこんなぶつぶつの穴ができるんだけどそれに似ていると自分は思う

上を見ると障子? だれか住んでたのかな?祠? どうやって運んだのだろう?
以上古座川峡での巖の巡礼でした とてもいいところですよ
2015年05月23日
熊野参詣道 雲取越 トレイルラン
那智から熊野本宮大社の熊野参詣道「雲取越え」をトレイルランしてきました。約1年前行ったときはテント泊でいきましたが、装備をもっと軽くすれば一日で行けるのでは?と思い計画を思いつきました。
那智駅にて車中泊し、夜明け前の4時に出発しました。いまは4時半になると明るくなってきますね。

大門坂までのアスファルト道をヘッデンつけてひたすら小走りです。ちなみに上り坂では無理をせず歩きます。無理して登り坂を走ると後がしんどい。
大門坂の杉の巨木群から鋭気をもらい身を引き締めます

那智の滝をみやり

登り口へ・・・小口までは歩きなら約5時間の行程 どこまで縮められるかな?(5時)

ただ、登立茶屋跡まで登りが続くので歩きですよ
舟見茶屋跡からの景色

ここらへから傾斜が緩やかになり走りやすい。気持ちよく小走りする。
地蔵茶屋に到着(7時) 東屋にて少し休憩 横になりました

何気に自販機あるんですね こんな山奥に・・・ 目覚めの一杯

苔むす古道をゆく (走ると滑りやすいので歩き)

巡礼者を見守る地蔵

小口からのすれ違う登山者。日本人より外国人のトレッキングの方たちのが多い 何人もすれ違いました

円座石は苔が前より少なくなったような・・・

8時30過ぎに小口に降り立つ 自販機でココアを購入。冷たい飲み物が美味しいです

パッキングの中身(バックパックはモンベルのフラットアイアンパック。コードを絞ることによってザックの中身が暴れるのを防ぎます)

赤い袋(S)は食糧 防水パック(オレンジ)に着替えとファーストエイドキットが入っています。ストームクルーザーは上だけを持参。リザーバータンクにはドリンクを1.5L入れてきました サイドポケットはパーゴワークスにモンベルの小さいポシェットです
食糧はこんな感じ。これにコンビニのおにぎり追加です けど余りましたからもう少し省いて良さそう

小口自然の家を通過して小雲取越えの登り口に向かいます。登り口手前の橋に注意書きが。見るとなんと小雲取越えの通行止のお知らせ まさか行けないのでは?と思っていましたが、迂回路があるとのことで一応林道経由で請川までいけるみたい。一安心
まさか行けないのでは?と思っていましたが、迂回路があるとのことで一応林道経由で請川までいけるみたい。一安心

桜茶屋跡まで登りが続く。太陽が燦々と降り注ぎ暑くてペースが落ちてきます。桜茶屋跡まで頑張ろうとやる気を引き起こします
茶屋について、東屋で靴を脱いで足裏をマッサージ。暑いので上半身も脱いだ。しばらく休憩
一年前もこの景色を見た 変わっていませんね(9:45)

休んでいると熊鈴の音が近づいてくるのが分かった。慌てて上着を羽織る。菅笠をかぶった男性で、通行止めの影響で、旅館の人に林道との合流地点まで送ってもらって、行程が早くなったとのこと。今日は小口自然の家に泊まる予定だったが、キャンセルして那智大社まで歩くことにするよう。あいさつを交わして足早に小口へ向かっていかれた。午前中に到着してキャンセルを申請するよう当日キャンセルって、お金取られるんじゃなかったっけ?
石堂茶屋跡を過ぎて、林道交差にでる。 通行止めの案内 「百間ぐら」からの景色を堪能したかったのに残念 どれくらい崩土したのだろう・・・


ここから林道をひたすら下る 小屋はトイレです

走ったり歩いたりしていたが、だんだん足の付け根が痛み出してきた。疲労も蓄積してきたので無理をせず、途中からずっと歩きに変更。
請川までもう少し。左にいくと温泉地

請川バス停付近に正午に到着~ JR那智駅から35㎞の道のりを約8時間で来れました。

ここから熊野本宮までいくのが感動的なのだろうけど、もうしんどいのでここでトレラン?は終了。新宮行のバスを待ちます。バスまでまだ時間があるのでお食事処「しもじ」で昼飯 時間を潰します。それでもまであるので、隣のデイリーヤマザキでラムレーズンのアイスを買ったり、疲れた体が甘いものを求めております。ハイドレーションに入れてきたスポーツドリンク1.5Lも丁度切れた。
13;26発の新宮行に乗る。請川バス停は時刻によってバス乗場が違うのでご注意ください。国道沿いと、駐在所付近と2か所あります。運営するバス会社も熊野交通と龍神バスとあるのでよく見ておかないといけない。

JR新宮駅に1時間ほどで到着。ここから那智への列車をまちます
サンマ寿司のオブジェ 初めて見ました ガリも再現

車窓から見える海がきれいだ・・・ 久しぶりに海を見た気がする

那智駅 温泉はボイラーの故障により臨時休業 残念

ここから車を走らせて串本へ 橋杭岩を見てさっぱりしようと「串本の温泉 サンゴの湯」に行きました

ここは料金がリーズナブルですね。温泉はしょっぱかった。塩水? すっきりしまして、オークワで買い出し。もちろんビールも購入。これから「望楼の芝」のオートキャンプ場に向かいます。 ここは広大な芝で人気があります。
有料区画と無料区画があります。シーズンによって利用できる区画が違います。 車からテントを運びだし設営。車を横につけられないのが残念なところですが、仕方がない

つーわけで自分へのご褒美と一杯やります「お疲れ様 」
」
チキンライス、サラダ アスパラの豚肉巻 濃いソース味を疲れた体が求めておりましたよ。これ以外に、サラミにクリームシチューとがんがん食べておりました。

以上 雲取越え トレランでした 次の日は古座に向かいました
那智駅にて車中泊し、夜明け前の4時に出発しました。いまは4時半になると明るくなってきますね。
大門坂までのアスファルト道をヘッデンつけてひたすら小走りです。ちなみに上り坂では無理をせず歩きます。無理して登り坂を走ると後がしんどい。
大門坂の杉の巨木群から鋭気をもらい身を引き締めます
那智の滝をみやり
登り口へ・・・小口までは歩きなら約5時間の行程 どこまで縮められるかな?(5時)
ただ、登立茶屋跡まで登りが続くので歩きですよ

舟見茶屋跡からの景色
ここらへから傾斜が緩やかになり走りやすい。気持ちよく小走りする。
地蔵茶屋に到着(7時) 東屋にて少し休憩 横になりました
何気に自販機あるんですね こんな山奥に・・・ 目覚めの一杯
苔むす古道をゆく (走ると滑りやすいので歩き)
巡礼者を見守る地蔵
小口からのすれ違う登山者。日本人より外国人のトレッキングの方たちのが多い 何人もすれ違いました
円座石は苔が前より少なくなったような・・・
8時30過ぎに小口に降り立つ 自販機でココアを購入。冷たい飲み物が美味しいです
パッキングの中身(バックパックはモンベルのフラットアイアンパック。コードを絞ることによってザックの中身が暴れるのを防ぎます)
赤い袋(S)は食糧 防水パック(オレンジ)に着替えとファーストエイドキットが入っています。ストームクルーザーは上だけを持参。リザーバータンクにはドリンクを1.5L入れてきました サイドポケットはパーゴワークスにモンベルの小さいポシェットです
食糧はこんな感じ。これにコンビニのおにぎり追加です けど余りましたからもう少し省いて良さそう
小口自然の家を通過して小雲取越えの登り口に向かいます。登り口手前の橋に注意書きが。見るとなんと小雲取越えの通行止のお知らせ
 まさか行けないのでは?と思っていましたが、迂回路があるとのことで一応林道経由で請川までいけるみたい。一安心
まさか行けないのでは?と思っていましたが、迂回路があるとのことで一応林道経由で請川までいけるみたい。一安心桜茶屋跡まで登りが続く。太陽が燦々と降り注ぎ暑くてペースが落ちてきます。桜茶屋跡まで頑張ろうとやる気を引き起こします
茶屋について、東屋で靴を脱いで足裏をマッサージ。暑いので上半身も脱いだ。しばらく休憩
一年前もこの景色を見た 変わっていませんね(9:45)
休んでいると熊鈴の音が近づいてくるのが分かった。慌てて上着を羽織る。菅笠をかぶった男性で、通行止めの影響で、旅館の人に林道との合流地点まで送ってもらって、行程が早くなったとのこと。今日は小口自然の家に泊まる予定だったが、キャンセルして那智大社まで歩くことにするよう。あいさつを交わして足早に小口へ向かっていかれた。午前中に到着してキャンセルを申請するよう当日キャンセルって、お金取られるんじゃなかったっけ?
石堂茶屋跡を過ぎて、林道交差にでる。 通行止めの案内 「百間ぐら」からの景色を堪能したかったのに残念 どれくらい崩土したのだろう・・・
ここから林道をひたすら下る 小屋はトイレです
走ったり歩いたりしていたが、だんだん足の付け根が痛み出してきた。疲労も蓄積してきたので無理をせず、途中からずっと歩きに変更。
請川までもう少し。左にいくと温泉地
請川バス停付近に正午に到着~ JR那智駅から35㎞の道のりを約8時間で来れました。
ここから熊野本宮までいくのが感動的なのだろうけど、もうしんどいのでここでトレラン?は終了。新宮行のバスを待ちます。バスまでまだ時間があるのでお食事処「しもじ」で昼飯 時間を潰します。それでもまであるので、隣のデイリーヤマザキでラムレーズンのアイスを買ったり、疲れた体が甘いものを求めております。ハイドレーションに入れてきたスポーツドリンク1.5Lも丁度切れた。
13;26発の新宮行に乗る。請川バス停は時刻によってバス乗場が違うのでご注意ください。国道沿いと、駐在所付近と2か所あります。運営するバス会社も熊野交通と龍神バスとあるのでよく見ておかないといけない。
JR新宮駅に1時間ほどで到着。ここから那智への列車をまちます
サンマ寿司のオブジェ 初めて見ました ガリも再現

車窓から見える海がきれいだ・・・ 久しぶりに海を見た気がする
那智駅 温泉はボイラーの故障により臨時休業 残念
ここから車を走らせて串本へ 橋杭岩を見てさっぱりしようと「串本の温泉 サンゴの湯」に行きました
ここは料金がリーズナブルですね。温泉はしょっぱかった。塩水? すっきりしまして、オークワで買い出し。もちろんビールも購入。これから「望楼の芝」のオートキャンプ場に向かいます。 ここは広大な芝で人気があります。
有料区画と無料区画があります。シーズンによって利用できる区画が違います。 車からテントを運びだし設営。車を横につけられないのが残念なところですが、仕方がない
つーわけで自分へのご褒美と一杯やります「お疲れ様
 」
」チキンライス、サラダ アスパラの豚肉巻 濃いソース味を疲れた体が求めておりましたよ。これ以外に、サラミにクリームシチューとがんがん食べておりました。
以上 雲取越え トレランでした 次の日は古座に向かいました
2015年05月11日
八経ヶ岳 テント泊 DAY2
2日目は4時半に起床。温度計を見ると5度くらい。寒いはずです。湯を沸かして鴨だしうどんを食す。そして珈琲で落ち着く。テントからでると月がてでいます。おや、今日も天気は良さげなのかな。
ルナ(月)とルナーソロ

テントを撤収して5時半すぎに狼平をあとにしました。昨日は私のテントと手前のグリーンのテント二つだけでした

高崎横手分岐を通過して
早朝の気持ちのいい森ハイク 鳥の囀りをききながら

朽ちた倒木から次世代の芽

朝の斜光が森に降り注ぎます

普通に下山するのは面白くないので、崩れている坪の内林道を歩いてみることに。比較的安全だろうと思ってたけど、岩の崩落個所もあり、ここは行くべきではありませんね。ちと反省

送電線のところからみたらい渓谷方面を望む

鉄塔の幾何学的なライン

天川村役場に戻ってきました(10時)

登山は終了しここから入浴しようと「天川薬湯センター みずはの湯」へ車を走らせました。しかしなんと準備中の札が まだ行くには早かったんだ。仕方ないのでこのまま車を走らせまして、道の駅 吉野路大塔の温泉に。しかしここも営業していない
まだ行くには早かったんだ。仕方ないのでこのまま車を走らせまして、道の駅 吉野路大塔の温泉に。しかしここも営業していない 平日は休みのよう・・・ 山と高原地図とにらめっこしてここから北上して「西吉野温泉」へ行くことにしました
平日は休みのよう・・・ 山と高原地図とにらめっこしてここから北上して「西吉野温泉」へ行くことにしました
そしてやっと空いている温泉施設にありつけました
西吉野温泉「きすみ館」です

ここでやっとさっぱりできました 行ったときは温泉は私一人で男湯を独占できました
以上ひさびさの大峯 八経ヶ岳 テント泊でした
ルナ(月)とルナーソロ
テントを撤収して5時半すぎに狼平をあとにしました。昨日は私のテントと手前のグリーンのテント二つだけでした
高崎横手分岐を通過して
早朝の気持ちのいい森ハイク 鳥の囀りをききながら
朽ちた倒木から次世代の芽
朝の斜光が森に降り注ぎます
普通に下山するのは面白くないので、崩れている坪の内林道を歩いてみることに。比較的安全だろうと思ってたけど、岩の崩落個所もあり、ここは行くべきではありませんね。ちと反省
送電線のところからみたらい渓谷方面を望む
鉄塔の幾何学的なライン
天川村役場に戻ってきました(10時)
登山は終了しここから入浴しようと「天川薬湯センター みずはの湯」へ車を走らせました。しかしなんと準備中の札が
 まだ行くには早かったんだ。仕方ないのでこのまま車を走らせまして、道の駅 吉野路大塔の温泉に。しかしここも営業していない
まだ行くには早かったんだ。仕方ないのでこのまま車を走らせまして、道の駅 吉野路大塔の温泉に。しかしここも営業していない 平日は休みのよう・・・ 山と高原地図とにらめっこしてここから北上して「西吉野温泉」へ行くことにしました
平日は休みのよう・・・ 山と高原地図とにらめっこしてここから北上して「西吉野温泉」へ行くことにしましたそしてやっと空いている温泉施設にありつけました
西吉野温泉「きすみ館」です
ここでやっとさっぱりできました 行ったときは温泉は私一人で男湯を独占できました

以上ひさびさの大峯 八経ヶ岳 テント泊でした
2015年05月11日
八経ヶ岳 テント泊 DAY1
久々にテント泊してきました。 大峯に全く行ってなかったので前回(冬季)敗退した八経ヶ岳に行くことに
天川村の役場に駐車させていただいて、5時に出発しました。
民家の所からスタート 家の裏から登って行きます

坂を登って行きます 林の中をあがっていき、送電線のあるところがひらけている
みたらい渓谷方面は雲海の中

朝の斜光の中、順調にいく。途中どこかで見たような人に追い越される・・・雰囲気が似ているが気のせいか・・・軽い挨拶をかわしハイペースで進んでいかれた

坪の内林道に合流 林道を少し歩きその脇から遭難碑のあるところを進む

新緑が瑞々しいですね

栃尾辻に到着。避難小屋があるがなかは暗い(7;45)

8時20分ごろ、カナビキ谷からの合流地点に到着。冬季この金引橋から上がってきたがかなりのラッセルでした・・・

冬季の様子

冬季私は白の矢印方向の斜面を直登しましたが、夏道はナメリ坂の東側を巻くようについていた


頂仙岳を巻いて高崎横手出合を目指す

高崎横手分岐に到着。ここから弥山へは狼平へのが最短。しかしまだ時間があるし、天気も良いのでレンゲ道で明星ヶ岳をピークハントしてから弥山に行くことにしました(9時半ごろ)

日裏山より

弥山辻を通過してすこし前鬼方面へ南下、大きく目立つテープ目印から明星ヶ岳へ。踏み跡もありますね(10;45)

南は釈迦ヶ岳が見える。大展望を堪能しましたよ
そこから八経ヶ岳はすぐです

天気もよく日曜日とあってたくさんの人が登られていました。団体さんたくさん。弥山ではまだ残雪があった。ベンチにザックをおろしてここでテントを張ろうと最初考えたがまだ時刻が11時半と早い。あと明日の天気は台風の接近もあって悪化するのでは?と思ったのでそれならここから1時間の狼平で幕営しようと決断。再びバックパックを背負い出発しますよ~。時間も体力もまだあります。これなら狼平に先にテントを張ってデポして周ったほうがよかったのかな

八経ヶ岳 双眼鏡で覗くと倒木が結構目立つ

大黒岩を通過して、木製の階段が現れると狼平に近づいていることが分かる。狼平の避難小屋の屋根が見えてきてあとわずかの所で木製の階段が土砂崩れで流されていた 土砂は狼平の手前まで来ていたのには驚いた。 悪天の時注意が必要だな・・・
土砂は狼平の手前まで来ていたのには驚いた。 悪天の時注意が必要だな・・・

狼平に到着(13時)して、テントを張れるところを吟味します。持参したテントは非自立型テントのルナーソロ。そのカタチから少し広めの場所が必要なので、避難小屋のすぐそばの所をチョイス。あとはペグがしっかり刺さるかどうかですがこれもクリアー
久々のシックスムーンデザインズの「ルナーソロ」です。前回は釈迦ヶ岳で幕営。 非自立型、トレッキングポールを支柱にして設営します。暑いときはフルオープンにするとテント内でも暑さを軽減します。これがステラリッジだと暑くていられないでしょうね。ただしこれはお日様があるうち。日が落ちるとフルメッシュテントなので保温性はありません。通気性抜群すぎて夜中は寒かった

お昼どき おなかも空いていたので、一杯やりますよ~
麦とホップ黒はかなり好きです。 ペットボトルの中は日本酒です この一杯のために登っている感じだな(笑)

このあと、お昼寝したり、ウォークマンで音楽を聴いたりと夕飯までの~んびり過ごす。ただ、気になったのはいたるところにある注意書き
「大きい方をした後の紙はもちかえってください」というのがありました。ということはここの沢の水は汚染されている可能性が大であるわけで、浄水器や煮沸消毒は必須だろうと思う。
夕飯を終えて歯磨きをして、19時にシュラフに潜り込む。風が強くテントをばたつかせる音を聞きながら寝ちゃいました
以上DAY1終了です
天川村の役場に駐車させていただいて、5時に出発しました。
民家の所からスタート 家の裏から登って行きます
坂を登って行きます 林の中をあがっていき、送電線のあるところがひらけている
みたらい渓谷方面は雲海の中
朝の斜光の中、順調にいく。途中どこかで見たような人に追い越される・・・雰囲気が似ているが気のせいか・・・軽い挨拶をかわしハイペースで進んでいかれた
坪の内林道に合流 林道を少し歩きその脇から遭難碑のあるところを進む
新緑が瑞々しいですね

栃尾辻に到着。避難小屋があるがなかは暗い(7;45)
8時20分ごろ、カナビキ谷からの合流地点に到着。冬季この金引橋から上がってきたがかなりのラッセルでした・・・
冬季の様子
冬季私は白の矢印方向の斜面を直登しましたが、夏道はナメリ坂の東側を巻くようについていた
頂仙岳を巻いて高崎横手出合を目指す
高崎横手分岐に到着。ここから弥山へは狼平へのが最短。しかしまだ時間があるし、天気も良いのでレンゲ道で明星ヶ岳をピークハントしてから弥山に行くことにしました(9時半ごろ)
日裏山より
弥山辻を通過してすこし前鬼方面へ南下、大きく目立つテープ目印から明星ヶ岳へ。踏み跡もありますね(10;45)
南は釈迦ヶ岳が見える。大展望を堪能しましたよ

そこから八経ヶ岳はすぐです
天気もよく日曜日とあってたくさんの人が登られていました。団体さんたくさん。弥山ではまだ残雪があった。ベンチにザックをおろしてここでテントを張ろうと最初考えたがまだ時刻が11時半と早い。あと明日の天気は台風の接近もあって悪化するのでは?と思ったのでそれならここから1時間の狼平で幕営しようと決断。再びバックパックを背負い出発しますよ~。時間も体力もまだあります。これなら狼平に先にテントを張ってデポして周ったほうがよかったのかな

八経ヶ岳 双眼鏡で覗くと倒木が結構目立つ
大黒岩を通過して、木製の階段が現れると狼平に近づいていることが分かる。狼平の避難小屋の屋根が見えてきてあとわずかの所で木製の階段が土砂崩れで流されていた
 土砂は狼平の手前まで来ていたのには驚いた。 悪天の時注意が必要だな・・・
土砂は狼平の手前まで来ていたのには驚いた。 悪天の時注意が必要だな・・・狼平に到着(13時)して、テントを張れるところを吟味します。持参したテントは非自立型テントのルナーソロ。そのカタチから少し広めの場所が必要なので、避難小屋のすぐそばの所をチョイス。あとはペグがしっかり刺さるかどうかですがこれもクリアー
久々のシックスムーンデザインズの「ルナーソロ」です。前回は釈迦ヶ岳で幕営。 非自立型、トレッキングポールを支柱にして設営します。暑いときはフルオープンにするとテント内でも暑さを軽減します。これがステラリッジだと暑くていられないでしょうね。ただしこれはお日様があるうち。日が落ちるとフルメッシュテントなので保温性はありません。通気性抜群すぎて夜中は寒かった
お昼どき おなかも空いていたので、一杯やりますよ~

麦とホップ黒はかなり好きです。 ペットボトルの中は日本酒です この一杯のために登っている感じだな(笑)
このあと、お昼寝したり、ウォークマンで音楽を聴いたりと夕飯までの~んびり過ごす。ただ、気になったのはいたるところにある注意書き
「大きい方をした後の紙はもちかえってください」というのがありました。ということはここの沢の水は汚染されている可能性が大であるわけで、浄水器や煮沸消毒は必須だろうと思う。
夕飯を終えて歯磨きをして、19時にシュラフに潜り込む。風が強くテントをばたつかせる音を聞きながら寝ちゃいました
以上DAY1終了です
2015年05月07日
高野山町石道
連休中、麓の九度山から高野山までの「高野山町石道」を歩いてきました。さて、この町石道ですが、これは弘法大師が母に会うために通った道を言うようです。弘法大師の母は息子(空海)の開いた山を一目見たいと思い、讃岐の国から訪れましたが、女人禁制の山なので、たとえそれが母親でも入山禁止。母親は九度山の政所(慈尊院)に滞在してここから、祈りを捧げていたよう。そのことに感動した空海が月に九度は山を下りたという逸話。地名の「九度山」の由来はココにあるようですね
夜中に出発して、道の駅「柿の郷くどやま」にて車中泊しました。以前行った日に、目星をつけてた駐車場は時間制限があって、夜中にはロープが張られて駐車できず
真田庵近くのP 六文銭が目印 夜間は駐車不可。 九度山駅から近いココにしようと思ったが残念

道の駅を5時に出発し、まずは慈尊院をめざします。
慈尊院も秘仏公開。女人高野のいわれのため ここは女性の乳房を模った絵馬が奉納されております。

そのすぐ先に丹生官省符神社。階段を上がるとすぐ
狩場明神と2匹のワンコ 弘法大師を高野山へと導いた神です

丹生官省符神社から脇に町石道があります。柿の畑を通り抜けます

先日購入したフォックスファイヤーのスコーロンを着こんでます。上半身はMサイズを購入。しかし家で気付いたけど、袖が長い。やっぱ試着してから買うべきだった。メーカーで長さが違うんだよな~。

道標の町石はかなりデカい。3Mくらいあるんじゃないか?1町(109M)ごとに配置してある。平安時代は木製の卒塔婆だったが老朽化のため、鎌倉時代に石に変更。約20年かけて整備されたようです。当然今のように車などあるわけもなく、馬とか牛に牽かせて、長い歳月をかけて・・・・ 苦労が偲ばれます。ちなみに8割以上が建立当時のままの町石です

柿の畑を抜けて、雨引山分岐点を通過し、7時ごろ六本杉に到着。ここから町石道をそれて世界遺産の「丹生都比売神社」へ寄り道しました

町石道をたんたんと辿りたい方はそのまま古峠へ。こちらのルートのが平坦です。丹生都比売神社へは下り坂。
丹生都比売神社の輪橋 淀君の寄進らしい(7:30)


室町時代に建立の楼門も朱色ですね。熊野速玉大社みたい ちなみに「丹」は「朱」のことで魔除けのために使われるのだとか
ちなみに祭られているのは女神で、天照大御神の妹さん「稚日女命」

本殿には近づけないので、見えるところから撮影。第一殿から第四殿ある。この創り、熊野本宮大社や速玉と同じですね

ここから二つ鳥居まで登り坂
途中にあったお遍路シール?どこで売ってるんだろう・・・

二ツ鳥居に着きました 当時は木製だったよう

近くの展望台から天野の里が一望できる

二ツ鳥居から下り坂、町石道はゴルフ場の脇を通っています。「ゴルフボールに注意」の看板や、対イノシシ用の電気柵など。
笠木峠で一休みしてから町石道は国道370号に沿っての上の方についている。バイクの音がけたたましい。
喧騒の中、我々の道中を見守る小さきお地蔵さん

矢立に到着。ここの茶屋で一福します(10時)

やきもちを二ついただきま~す

冷たいお茶もいただき、ここから先の登り坂に備えます
弘法大師にまつわる石を見やりながら大門まで一気に行きました
袈裟掛石 この石の隙間を通れると長生きするらしい。私には無理っす 子供しか通れないんじゃね?

白装束の方とすれ違い、大門に正午ごろ到着 麓の九度山から7時間かかりました

ここから壇上伽藍へ ここに慈尊院からの町石道「1」があります

連休中とあって人がかなり多い。せっかくきたのだから自分へのご褒美と精進料理でも奮発して食べようかと思ったがどこも満席 しかたないのでコンビニの惣菜パンでガマン
しかたないのでコンビニの惣菜パンでガマン
壇上伽藍を散策します
高野山の守護神を祀る御社 丹生都比売神社から勧請した神を祀る 女人禁制だった時代なのに女神はOK?

西塔は根本大塔にくらべてシックな感じ ただこっちのが落ち着いた感じでいいですね

御朱印は長蛇の列 なにがそんなにいいのかな・・・

六角経蔵 基壇付近にある取っ手がついていて、これで一周することによって一切経を一通り読経した功徳得られるという。ただし大人数人がいないと動かない お遍路さんたちが動かしては歓喜しておりました

霊宝館に再び訪問して、秘仏拝見。すごい人だかりで見るのも一苦労します。お土産に生ごま豆腐を購入して、女人堂へ向かう。せっかくだし端っこまで歩きました
女人禁制の時代に女性のための参籠所 現存する唯一の建物 ここでも御朱印の列が!
ここには弁財天が祀られておりました

ここからバス待ち 高野山駅までバス専用道路で行きます。連休中とあって臨時がでていましたよ。駅で切符を買いケーブルカーに
満車で一本見送りましたが、車両の下に極太ケーブルがありこれで車両を上げ下げしているのだろう。アプト式とは違うんですね

極楽橋駅に到着 1番線に入線する折り返しの普通列車橋本行きを待ちます
こっちは特急こうや 普段の赤と白のカラーリングとは違いますね。 ちなみに特急券はすべて売り切れだそう

橋本行きの普通列車には座れず九度山まで立ちっぱなし。疲労のせいか立ったままうたた寝してしまう。そのたびに膝がカクンとなり、ハッと目が覚めます。 久々に南海に乗れたよ

駅から道の駅まで歩いて「高野山町石道」の踏破完了です

参考書籍 楽学ブックス 古寺巡礼「高野山」 JTBパブリッシング
参考地図・時間配分等 わかやま観光情報よりダウンロード・印刷できます

夜中に出発して、道の駅「柿の郷くどやま」にて車中泊しました。以前行った日に、目星をつけてた駐車場は時間制限があって、夜中にはロープが張られて駐車できず
真田庵近くのP 六文銭が目印 夜間は駐車不可。 九度山駅から近いココにしようと思ったが残念
道の駅を5時に出発し、まずは慈尊院をめざします。
慈尊院も秘仏公開。女人高野のいわれのため ここは女性の乳房を模った絵馬が奉納されております。
そのすぐ先に丹生官省符神社。階段を上がるとすぐ
狩場明神と2匹のワンコ 弘法大師を高野山へと導いた神です
丹生官省符神社から脇に町石道があります。柿の畑を通り抜けます
先日購入したフォックスファイヤーのスコーロンを着こんでます。上半身はMサイズを購入。しかし家で気付いたけど、袖が長い。やっぱ試着してから買うべきだった。メーカーで長さが違うんだよな~。
道標の町石はかなりデカい。3Mくらいあるんじゃないか?1町(109M)ごとに配置してある。平安時代は木製の卒塔婆だったが老朽化のため、鎌倉時代に石に変更。約20年かけて整備されたようです。当然今のように車などあるわけもなく、馬とか牛に牽かせて、長い歳月をかけて・・・・ 苦労が偲ばれます。ちなみに8割以上が建立当時のままの町石です
柿の畑を抜けて、雨引山分岐点を通過し、7時ごろ六本杉に到着。ここから町石道をそれて世界遺産の「丹生都比売神社」へ寄り道しました
町石道をたんたんと辿りたい方はそのまま古峠へ。こちらのルートのが平坦です。丹生都比売神社へは下り坂。
丹生都比売神社の輪橋 淀君の寄進らしい(7:30)
室町時代に建立の楼門も朱色ですね。熊野速玉大社みたい ちなみに「丹」は「朱」のことで魔除けのために使われるのだとか
ちなみに祭られているのは女神で、天照大御神の妹さん「稚日女命」
本殿には近づけないので、見えるところから撮影。第一殿から第四殿ある。この創り、熊野本宮大社や速玉と同じですね
ここから二つ鳥居まで登り坂
途中にあったお遍路シール?どこで売ってるんだろう・・・
二ツ鳥居に着きました 当時は木製だったよう
近くの展望台から天野の里が一望できる
二ツ鳥居から下り坂、町石道はゴルフ場の脇を通っています。「ゴルフボールに注意」の看板や、対イノシシ用の電気柵など。
笠木峠で一休みしてから町石道は国道370号に沿っての上の方についている。バイクの音がけたたましい。
喧騒の中、我々の道中を見守る小さきお地蔵さん
矢立に到着。ここの茶屋で一福します(10時)
やきもちを二ついただきま~す
冷たいお茶もいただき、ここから先の登り坂に備えます
弘法大師にまつわる石を見やりながら大門まで一気に行きました
袈裟掛石 この石の隙間を通れると長生きするらしい。私には無理っす 子供しか通れないんじゃね?
白装束の方とすれ違い、大門に正午ごろ到着 麓の九度山から7時間かかりました
ここから壇上伽藍へ ここに慈尊院からの町石道「1」があります
連休中とあって人がかなり多い。せっかくきたのだから自分へのご褒美と精進料理でも奮発して食べようかと思ったがどこも満席
 しかたないのでコンビニの惣菜パンでガマン
しかたないのでコンビニの惣菜パンでガマン壇上伽藍を散策します
高野山の守護神を祀る御社 丹生都比売神社から勧請した神を祀る 女人禁制だった時代なのに女神はOK?
西塔は根本大塔にくらべてシックな感じ ただこっちのが落ち着いた感じでいいですね
御朱印は長蛇の列 なにがそんなにいいのかな・・・
六角経蔵 基壇付近にある取っ手がついていて、これで一周することによって一切経を一通り読経した功徳得られるという。ただし大人数人がいないと動かない お遍路さんたちが動かしては歓喜しておりました

霊宝館に再び訪問して、秘仏拝見。すごい人だかりで見るのも一苦労します。お土産に生ごま豆腐を購入して、女人堂へ向かう。せっかくだし端っこまで歩きました
女人禁制の時代に女性のための参籠所 現存する唯一の建物 ここでも御朱印の列が!
ここには弁財天が祀られておりました
ここからバス待ち 高野山駅までバス専用道路で行きます。連休中とあって臨時がでていましたよ。駅で切符を買いケーブルカーに
満車で一本見送りましたが、車両の下に極太ケーブルがありこれで車両を上げ下げしているのだろう。アプト式とは違うんですね
極楽橋駅に到着 1番線に入線する折り返しの普通列車橋本行きを待ちます
こっちは特急こうや 普段の赤と白のカラーリングとは違いますね。 ちなみに特急券はすべて売り切れだそう
橋本行きの普通列車には座れず九度山まで立ちっぱなし。疲労のせいか立ったままうたた寝してしまう。そのたびに膝がカクンとなり、ハッと目が覚めます。 久々に南海に乗れたよ
駅から道の駅まで歩いて「高野山町石道」の踏破完了です
参考書籍 楽学ブックス 古寺巡礼「高野山」 JTBパブリッシング
参考地図・時間配分等 わかやま観光情報よりダウンロード・印刷できます